「シンキングペンシルの使い方を覚えることがバチパターンで釣果を伸ばすための秘訣です!」こう語るのはシーバスを求めて全国各地を飛び回るエキスパート・橋本康宏さん。バチパターンでシンペンを使用するメリットと基本的な使い方を教えてもらった。
「シンキングペンシルの使い方を覚えることがバチパターンで釣果を伸ばすための秘訣です!」こう語るのはシーバスを求めて全国各地を飛び回るエキスパート・橋本康宏さん。バチパターンでシンペンを使用するメリットと基本的な使い方を教えてもらった。
写真◎浦 壮一郎 文◎編集部
バチ抜けにはシンキングペンシル
バチパターンとは産卵のために抜け出たゴカイの類がメインベイトとなるパターン。川で抜ける川バチと海で抜ける港湾バチに分けられる。川バチは普段河口付近の砂泥などの中で生活しているが、例年2月頃になると大潮後の中潮で産卵のために水中へと泳ぎ出し、くねくねと身体を曲げながら流れに乗って降っていく。海で抜けるバチと比べて体長は10~15cmと大型なのが特徴だ。泳ぐと言っても流れに逆らうほどの遊泳力はなく流れのヨレや流心に集まりやすいため、シーバスも同じようなポイントに定位しながら流下してくるバチを捕食している。バチさえ抜けていれば橋脚などのストラクチャーがないオープンエリアでも釣ることができるため、他のベイトパターンのように明暗など固執する必要はない。
バチパターンで主に使用するのはバチのシルエットに近い細身のペンシルベイトやフローティングミノー。川バチの場合は11~12cmのルアーが多用される。また、バチは一定のレンジを保って流下する、引き波を立てながら泳ぐなどの特徴を持っているためレンジキープ力や引き波を立てる能力に優れた設計となっているものが使いやすい。

河川で見られるバチは10 ~ 15cm。細身で同じくらいの長さのシンキングペンシルでバチを捕食しているシーバスをねらう
「僕がバチ抜けパターンでよく使っているのはシンキングペンシルです。フローティングのルアーに比べてメリットが多いと感じています」
こう語るのは神奈川県在住の橋本康宏さん。東京湾奥をホームグラウンドとしているエキスパートだ。シンキングペンシル(シンペン)を使用するメリットは主に3つ。
一つ目はロングキャストで広範囲を探れること。リップなどの空気抵抗となるパーツがなくフローティングのルアーよりもウエイトがあるため潮目や流心、流れのヨレなどのバチが溜まりやすいポイントが沖に形成されている状況でもルアーを送り込むことができる。横風や向かい風などの悪条件下でもロングキャストが可能だ。
二つ目はレンジを自在に調節できること。フローティングミノーは潜行深度に制限があるが、リトリーブスピードやロッドの角度などのアングラー側の入力で好みのレンジを探ることができるシンペンならボトム付近を流れるバチも演出できる。
三つ目は引き波の表現が多彩なこと。水面直下での繊細なレンジ操作ができるため、ハッキリとした引き波からモヤモヤとした引き波まで大きさや形状を調整しやすい。
「シンペンはアングラーの操作によって多彩なアプローチが可能です。一つのルアーでさまざまな状況に対応できるのが強みですね。また、多くのアングラーがフローティングのルアーを使用しているためか、シンペンはスレたシーバスにも効果的だと感じています」
-1.jpg?width=730&height=1097&name=s-03(2)-1.jpg)
シンキングペンシルの飛距離なら沖のポイントにもアプローチできる
シーバスは引き波をよく見ている
橋本さんが愛用しているシンペンはマニックシリーズ(デュオ)。テール下がりの水中姿勢となるウエイトセッティングと細身のボディー形状によって飛距離を稼ぎやすくなっている。
「立ち込まないと届かないような沖めのポイントでも射程圏内になるほどの飛距離を出せるのが魅力です。また、どのモデル、サイズでもマニックムーヴという共通のアクションをするのでローテーションしても使用感が変わらないのも気に入っています」
「マニックムーヴ」とはハイピッチなタイトロールが特徴のアクション。バチが生み出すものに近いV 字の引き波の中に弱いウネリを加えることができるため単調な引き波に比べてアピールが強くなるという。マニックにはオリジナルモデルに加えウエイトが軽く、ゆっくりとリトリーブすることができるスローモデルもある。橋本さんは主に流したいレンジと引き波の大きさで使い分けているという。表層でヘッドを出した状態で大きな引き波を立てて誘いたい場合(=ハイアピール)や速い流れの中でもアップで引き波を立てたい場合はスローモデルが、水面直下で落ち着いた引き波を立てたい(=ローアピール)、もしくはさらに深いレンジやボトムを探りたい場合はオリジナルモデルが活躍する。シーバスの活性や表層のバチの有無などに応じてアピール力や流すレンジを決めるのがよいだろう。

マニックの引き波。水面直下を泳ぎもやもやとしたV 字の引き波を立てる

マニックスローの引き波。マニックよりもヘッドが浮き上がりやすいためハッキリとした引き波が立つ
「ボートシーバスで魚探を見ていた時、水深9mに何尾かのシーバスが溜まっていました。シーバスたちは引き波を立てずに使っていたルアーには無反応でしたが、引き波を立てた途端にものすごい勢いで突き上げてきたことがあります。シーバスの感覚は侮れません」
バチパターンの場合、ルアーサイズは河川のバチの大きさにマッチしやすい115をベースに、遠投したい場合は135、橋脚などのピンスポットをねらう、もしくはアミや港湾部のバチなどの小さなエサを捕食している場合は95や75をチョイスしているそう。

マニックはバチのみでなくアミパターンやハクなどのベイトパターンにも使用できる。飛距離を活かしたアプローチで明暗の攻略も可能だ
流れに同調させるのがキモ
流れに乗った状態で一定のレンジを漂っていくバチを演出するためにはルアーの速度やレンジを保つことが大切。ルアーを流れと同調させながら表層付近をじっくりとドリフトで探っていくのが基本の探り方だという。同調とはルアーを流れに乗せたままアクションとレンジを安定させることだ。具体的な手順は次のとおり。
(1)アップクロスにキャストする
(2)着水したら素早くラインスラックを巻き取る
(3)スローリトリーブしながらルアーを流れに乗せる
(4)自分から見て斜め45度下流まで流したら回収してはじめにもどる
ラインと水面の角度が大きくなるとルアーが上方向に引っ張られてしまい、流れる速さやレンジ、アクションが不安定になってしまう。ルアーが近づいてくるにつれてロッドを下げていき、角度をなるべく一定に保つことが重要だ(イラスト参照)。リーリングはラインが水に付かない程度に弛ませた状態で行なう。アップ~ダウンにかけて徐々に遅くしていくとルアーを流れに乗せたまま誘うことができる。リーリングの速度は流れているルアーの同調具合を観察しながら調節しよう。
「バチを捕食しているシーバスはとても弱い力でルアーを吸い込むため、弛みができるくらいのラインテンションを保つようにするとフッキング率が上がります」
橋本さんはバチパターンではレンジと流す筋が合っていることが最重要で、カラーはバイトに至らせるための最後の一押しだと考えているという。
「同じ立ち位置から投げ続ける場合が多いため、カラーローテーションによって目先を変えるのが効果的です。また、フィールドの状況に応じたカラーチョイスも釣果UP のカギとなります」
アピールが強い順からマットチャート系、透け感があるゴーストチャート系、地味系があると安心。基本的には視認性重視のカラーチョイスがよいそうだが、目立つカラー以外で目先を変えることによってコンスタントに釣ることや食い渋っている状況を打破することができる場合も多いという。
また、これらの基本色にプラスしてブラック系、クリア系ももっておくと安心だという。ブラックはシルエットがハッキリするため真っ暗な場所での実績が高く、クリアは月夜や都市河川などの水面の明かりが強い時やハイプレッシャーなポイントで活躍するそうだ。

「とりあえず揃えるならコレ!」というカラー例。マニックスロー115 のマットピンクギーゴ、ゴーストパールチャート、マットミントギーゴ( 新色)、ピンクスカッシュLG テール、マットブラックPB Ⅱ


同じチャートカラーでも透け感によってアピール力は異なる。シルエットがハッキリと出るマットチャート(写真はマットピンクギーゴ)のほうが光を透過するゴーストチャート(写真はゴーストパールチャート)よりもアピール力は強い
見えなくてもバチは流れている
ボイルがない、もしくは表層に見えていなくてもバチはボトム付近を流れている可能性がある。基本の探り方で反応がない場合はルアーを通すレンジを下げると途端に釣れることも。ボトム付近を探る場合、まずは着水後にルアーをボトムまで沈める。そのあとはラインスラックを少しずつ回収するようなイメージで表層での誘い方に比べてゆっくりとリトリーブしながらルアーを流す。ラインが流されてテンションが掛かってしまうとルアーが浮き上がりやすくなるため、ラインが水面にベタッと付いてしまうのはNGだ。また、深場をじっくりと探りたい時や風が強い時はスローモデルにくらべて浮き上がりにくいオリジナルモデルをチョイスするほうがレンジやアクションを安定させやすいという。

アップクロスにキャストしてロッドを45 度に立てながらリトリーブする

ルアーが近づいてくるのに合わせてロッドを徐々に倒していく。巻き抵抗を一定に保てるようにリトリーブ速度も落とす。流れていくルアーをティップで追い、ラインとロッドを一直線にすると程よい弛みを保つことができ、シーバスの吸い込みを邪魔しない
シンキングペンシルの使い方をマスターすればさまざまなフィールドや釣法に応用できるため、さらなる釣果UP につながること間違いなしだ。

橋本さんは弱い吸い込みでもハリ先が魚の口内に残りやすいように常に新品のフックを使う。ルアーを使う前に現地で装着するという徹底ぶりだ

スナップはルアーの動きを妨げにくい細軸・小さめを使用する
※このページは『つり人2024年4月号』を再編集したものです。



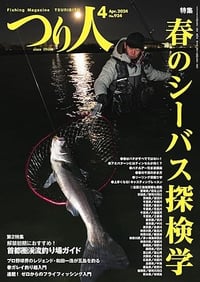

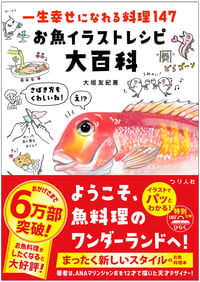





.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)





%20(2).jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)


