手軽に楽しめる港はアプローチしやすく多くの釣り人から人気だ。そこで釣果を伸ばすには港の構造を知るのが一番だろう。港工事を施工している専門業者に話を聞いてみた。
港で釣果を伸ばすには構造を知ってしまうのが一番だ。北海道の南を中心に数々の港工事を施工してきた専門業者に造り方を聞いた
構造を知ってればもっと釣れる

上の写真は右から壁がケーソン、根固めブロック、被覆ブロックと設置されている。港内で釣りをする場合、アングラーがエントリーするのは岸壁と防波堤だ。その定義は、船を係留させたり、漁師さんが荷揚げなどの作業を行なう場所は岸壁。港内の静穏を保つのを目的に造られたのが防波堤で、外海側、港内側の両面が水に接している。港内に突き出るような突堤や埠頭も、どちらの面も水になっているが、どのように造られているのだろう?ロックフィッシュねらいで定番の穴撃ちだが、実際、海底はどうなっているのか?そこ(底) が分かれば攻路の糸口が見つかるはずだ。そこで、函館に本社を置き、道内外で多くの港湾、漁港の建設および水産関連施設(魚礁、増殖礁)造成などの海洋土木事業を手がけている株式会社菅原組に、港の建造物の造り方を教えていただいた。

「海洋土木北海道No.1を目指す」をモットーに、1958年に松前町で創業。高い技術力と実績があり、農林水産大臣をはじめ、北海道開発局、北海道知事など多方面から表彰や感謝状を授与されている。地域貢献や環境保全にも力を入れていて、函館市大森浜の海岸清掃や、創業地の松前町では植樹を行ない、地域住民からの信頼も厚い。住所:函館市浅野町4番16号 TEL:0138-44-3710
詳しい工法に移る前にまずは魚の付き場について紹介したい。
魚の付き場

上の写真は根固めブロックを設置しているところだ。根固めブロックは底が平らで、基礎マウントに密着するように設置される。穴のないただの箱型もあるが、穴の開いたタイプもある。被覆ブロックに比べて大きく、穴も深くなる。穴撃ちをしていて足もとに深い穴が見えることがあるが、根固めブロックの穴である可能性が高い。

こちらは被覆ブロックを設置しているところ。被覆ブロックは大抵、脚があり、基礎マウントとブロックの間に隙間ができる。砂で埋まっていない場合は、被覆ブロックの下を魚が通り抜けることができるそうだ。作業で潜っていると、ソイやガヤ(エゾメバル)、カジカは底点の穴(被覆ブロックの穴)の中にいることが多いと感じるそうだ。

ガヤ(エゾメバル)。他の釣りでゲストとして釣れることが多く、ねらう人は少ないが、適切なタックルで釣ると楽しい

ケムシカジカ。箸でなべ底を突っついて壊してしまいそうなくらいおいしいから「鍋壊し」と呼ばれるほど美味

一方、上のアイナメは泳いで行けるスリットを好むことが多く、岩の間や、被覆ブロックの隙間で見かけるという。隙間をスーッと泳いでいて、行き止まりになったら、ブロックの上を泳いで、また隙間に潜っていく。また、コンブは下まで生えていると思っている人が多いかもしれないが、じつは底までびっしり生えていることはなく、岸壁などでは潮の満ち引きで出たり入ったりする部分に上下1mほどの幅でしか生えていない。その下をアイナメが泳いでいることも少なくないそうだ。なお、場所打ち式コンクリート工法で新しく防波堤や岸壁を造った場合、コンクリートの内部が完全に冷えまるまでの1ヵ月くらいは熱を発生しているらしく、微生物やアワビなどが集まりやすい。それを捕食するために魚も巣まるのか、新しくできた場所はすぐに魚が釣れることが多い。施工場所や規模、工法によって違いはあるものの、あくまでも標準的な漁港の防波堤工事で20m造ると仮定すると、石を敷き、コンクリートブロックやケーソンを造って設置して仕上げるのに施工時間として半年ほどの時間がかかるそうだ。ケーソンの設置所要時間だけだと3時間ほど。午前1個、午後1個のペースで設置できる。途中で止めることはできず、その日のうちに固定までの作業を行なわなければならない。
代表的な工事方式3選
工事方式について詳しく話を聞いてみたところ、そもそも防波堤や岸壁は規模によって工事方式が違うそうだ。一般的なのは大きく分けて3つ。
①漁港などの小規模な岸壁などは、ほとんどが座上で造った型枠をクレーンで水中に設置し、水中でも固まる水中コンクリートを流し込む『場所打ち式コンクリート工法』


②小~中規模の防波堤や突堤などは、陸上で造ったコンクリートブロックを、クレーンを使って積み上げていく『積みブロック工法』

③大型港など大規模な場合は、『ケーソン工法』という箱状のコンクリートを造って設置する方法を採用している。

ちなみに、ケーソンとはフランス語で「箱」を意味する言葉からきている。それらを見分ける方法は、釣り人が立っている上部コンクリート部分ではなく、その下に見えている水中から出てきている部分を見て判断できる。凹凸がなく平らであれば枠を使って造る『場所打ち式コンクリート工法』コンクリートブロックとケーソンの見分けは難しいようだが、1ブロックの長さは『場所打ち式コンクリート工法」で5m、『ケーソン工法』だと10mが多いことから、つなぎ目の間隔が10mで、ブロックの横並びが多少でもズレていればケーソンと判断できる。ちなみに、室蘭港や函館港の沖防波堤はケーソン。小機港の南防波堤もケーソンだが、北防波堤は積みブロックの一種である「傾斜ブロックエ法』で施工されている。釣り人の会話でもよく耳にするケーソンだが、その設置工事について次から紹介したい。
工事が行なわれる港に、“フローティングドック”といわれる大きな作業台のある四型船を係留し、その船上で同時に数個のケーソンを製作する。完成したケーソンは、そのまま沖の仮置き場近くまで運ばれて降ろすが、ケーソンは重いためクレーンでは持ち上げることはできない。降ろす方法は何と!ケーソンが浮くまで船を沈め、ケーソンが浮いたら引船で引っ張り出すのだ。船内のタンクに海水を注排水することで船体を浮き沈みさせることができるそう。

内側が空洞になった箱状ゆえ、ケーソン自体は水に浮く構造になっている。浮いたケーソンは船でえい航され、仮置き場に選ばれる。そのままでは流されてしまうが、内部に水を注入することで沈み、着底させて固定することができるそうだ。その際、満潮時でもケーソンが水没しない水深に仮置き場は調整されている。この作業を繰り返し、必要な個数のケーソンが造られる。

新設する場所には、あらかじめ捨石と呼ばれる石により、基礎マウントが造られる。基礎マウントの表面は、ダイバーによる手作業で平らに石が敷き詰められていて、その上にケーソンを設置する。仮置き場のケーソンは内部の水を抜くことで再浮上させることができ、新設する場所までえい航される。
本設でも、まず内部に水を入れ、沈めて着底させる。その後、比重の高い砂や砕石を投入することで重量が増し動かなくなる。水はあふれるが全部が抜けるわけではなく飽和状態で終了。
よく、ケーソンとケーソンの間に隙間があり、水が通り抜けている場所があるが、もともと設置の際に数cmのクリアランスを設けているため、それが正常な状態とのこと。もし、クリアランスがなければ、設置の際、ケーソンどうしがぶつかり、破損してしまう危険性が高くなる。
設置場所は満潮時でも水没しないよう、マウントによって水深が調整されている。設置後は基礎捨石の流出を防ぐ目的で根固めブロックと被覆ブロックを設置する。大型の防波堤がケーソンで造られるのは、使われるコンクリートの量が少なく経済的だから。さらに、場所打ち式で造られた物は壊さなければ交換できないが、ケーソンは上部コンクリートを外し、内部の砂を取り除けば再浮上させることができる。交換中補修が容易なメリットがあるのだ。ケーソンの上部はコンクリートで蓋がされるため、施工後は内部を見ることはできない。私たちが立っている部分は、上部コンクリートと呼ばれる場所で、胸壁もその一部。外海に面している場合は、ケーソンや基礎部分に当たる波の力を弱めるため、消波ブロックが積まれることが多い。また、防波堤も消波ブロックも港内の静穏を保つのが目的なので、多少波が越えても静想が保たれる計算になっていることが多い。港内の突堤や単壁の下が空洞になっているのを見ることがあるが、あれは波を逃がし、波の衝撃をかわすためで、ケーソンの穴ではない。積みブロックの岸壁に多いという。
※このページは『根魚釣り北海道』を再編集したものです。
あわせて読みたい
・釣り糸の結び方!簡単な結びは?最強なのはどれ?強度実験も交えて解説
【2023年】釣り用偏光サングラスおすすめ人気ランキング14選
【投げ釣り】遠投できる投げ方の基本を解説! 目指せ200m超!

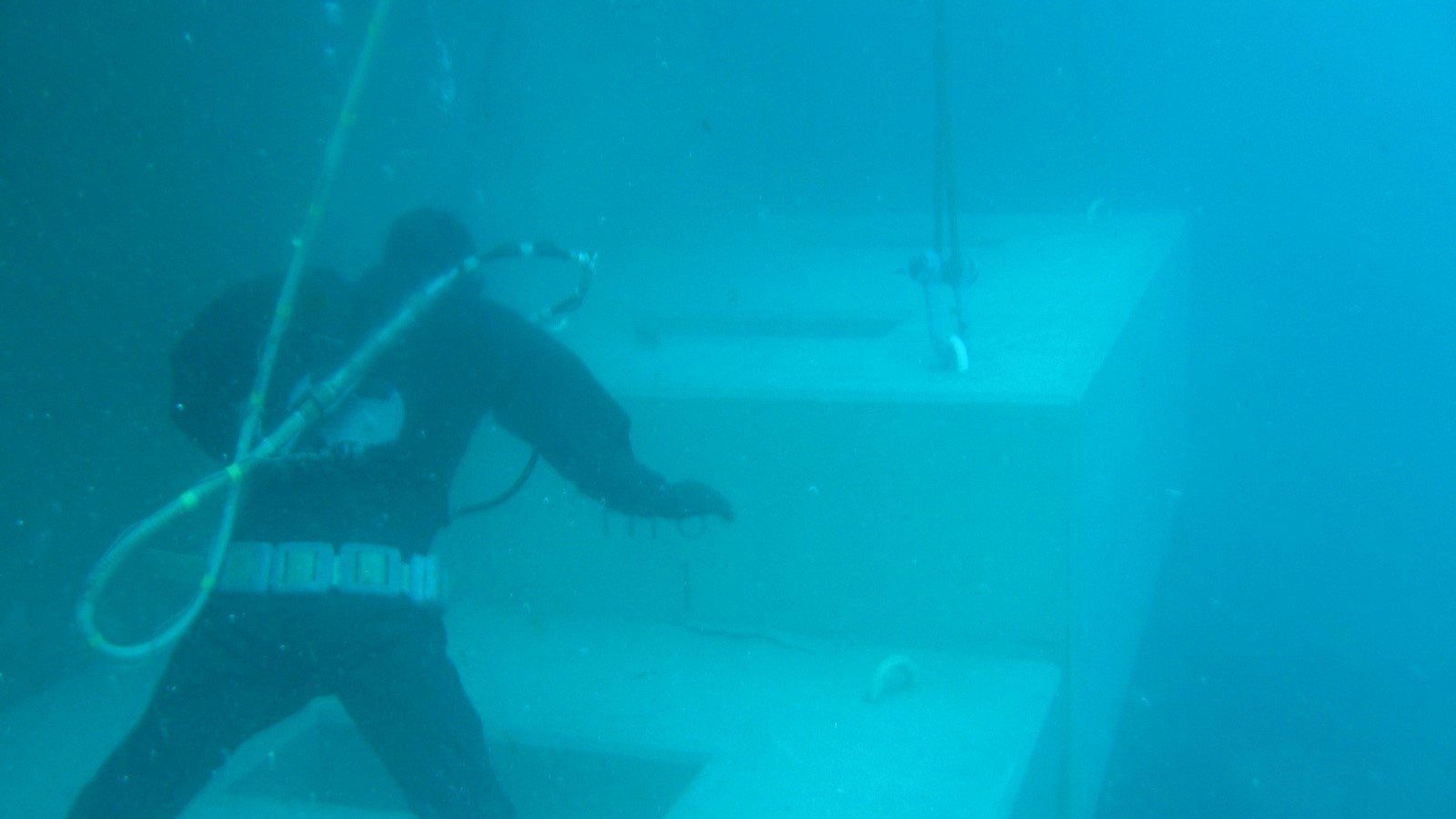
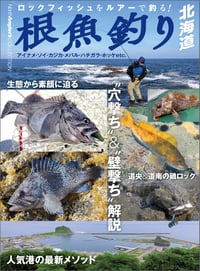

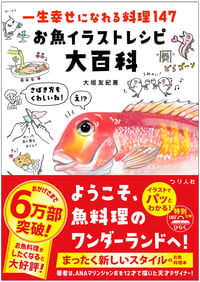


.jpg)

.jpg)








%20(2).jpg)


.jpg)

.jpeg)


.jpg)




.jpg)

