今夏、踏み潰しそうなほどに天然アユが充満しているのが福井県若狭湾に注ぐ南川と北川だ。そして今年はリールを使ったアユルアー(アユイング)を試行許可。この情報を聞きつけ解禁日から通い込んでいるのが西浦伸至さんだ。密度が濃いから数が出るのはもちろん、釣果を伸ばすルアーアクションを見出すのが面白いという。
かつて、水辺の危険を伝えていたのは「カッパに注意」という看板でした。それは子どもの想像力に働きかける警告でしたが、今はフェンスが張り巡らされ、自然そのものが遠い存在になっています。
私たちは安全を優先するあまり、自然への畏怖や命の手触りを知る機会を奪ってはいないでしょうか。近年喧伝されるSDGsも、原体験を欠いたまま語られては、空虚なスローガンに過ぎません。現代の社会が抱える違和感に向き合い、なぜ今、自然体験が真の「生きる力」となるのかを紐解きます。
レポート◎山根和明(株式会社つり人社代表)
協力◎株式会社龍角散、宇津救命丸株式会社、樋屋製薬株式会社
カッパは絶滅危惧種!? 水辺から消えた注意看板
あれはたしか私が8歳、兄が10歳の夏休み。母の実家がある福岡県柳川市へ帰省し、祖父母の家の周りに張り巡らされた掘割(クリーク)で、兄と二人でフナ釣りをしていました。
サオは祖父が作ってくれた1.5mほどの竹ザオ。子どもが扱うにはちょうどいい長さ。けれど、釣っているうちに沖の深みのほうが釣れる気がしてきます。少しでも遠くへウキを打ち込もうと、私たちは岸ぎりぎりに立ちました。そのとき、兄がバランスを崩して、まさかの落水。咄嗟に私は竹ザオを差し出し、兄はそれを掴んでどうにか這い上がりました。
「お前は俺の命の恩人だ」 兄は息を荒げながらそう言いました。「おんじん」――その言葉を、私は初めて知りました。全身ずぶ濡れになった兄と家に戻り、祖母に顛末を話すと、彼女はほっと息をつきながら言いました。 「カッパに連れて行かれんでよかったねえ。釣りばするときは、カッパに気を付けんといかんとよ」優しく叱るその口調に、どこか本気の気配がありました。
祖父母の家がある柳川は、北原白秋や檀一雄を輩出した水の都。市内には総延長930kmにも及ぶ掘割が張り巡らされ、水とともに暮らす町でした。当時の掘割はまだほとんどが素掘りで、マブナやタナゴ、オイカワ、ライギョなどが子どもでも簡単に釣れました。
土手には「キケン!カッパに注意」と書かれた看板が立てられており、描かれたカッパの顔はどこか愛嬌があって、恐ろしさよりも親しみを感じさせるものでした。けれど、私は知っていました。本物のカッパは恐ろしいと。たいていの本には、カッパは元来夜行性で、昼は水底でじっと潜み、夕方になると活動を始め人を水中に引き込む。好物は子どもだと記されていました。だから、私たちは「水辺では一人で遊ばない」、「夕方以降は近づかない」、「暗くなったら水辺から離れたところを歩く」といった教えを、カッパの名のもとに守っていたのです。

想像力で守るか、物理的に遠ざけるか
それから30年ほどの歳月が経ち、私がつり人編集長となり、柳川を訪れたときのこと。町を歩いてみても、あの「カッパ注意!」の看板がどこにも見当たりません。もしやと思い、編集部に戻ってから全国の執筆者に「カッパの看板を見かけたら写真を送ってほしい」とお願いしました。
しかし、届いた報告はゼロ――。 あれほど各地に〝生息〟していたカッパが、いつの間にか絶滅していたのです。代わりに土手はコンクリートで護岸され、柵やフェンスが整備され、子どもたちが水辺へ近づくことができなくなってしまったのです。物理的に子どもたちを水辺から遠ざけるか、それともカッパの看板を立てて、想像力で守るか。子どもの未来にとって、本当にいいのはどっちだったのでしょうか。
-Nov-25-2025-02-46-51-2665-AM.jpg?width=1280&height=720&name=03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-25-2025-02-46-51-2665-AM.jpg)
-4.jpg?width=1280&height=720&name=04r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-4.jpg)
カエルの共食い。釣りが教える「残酷な現実」
私が初めて釣った魚はライギョでした。7歳の夏、柳川で祖父に教わって釣りました。竹ザオにイト、ハリという実にシンプルな道具立て。エサは田んぼのあぜ道を飛び跳ねている3~4cmのカエル。
「ほら、あそこにいるよ」 祖父が指さす水面を見ると、木片のようなものが静かに浮いています。捕まえたカエルのお尻にハリをちょんと掛け、サオを操作してその木片の端にそっと降ろすと、次の瞬間、水柱が上がり、サオ先が一気に引き込まれました。木片だと思っていたのは、30cmほどのライギョだったのです。あの一尾で、私は釣りの世界に一気に引き込まれました。
当時の柳川には、子どもでも簡単に釣れるほど、ライギョがたくさんいました。兄弟で並んで釣れば、たちまち競争になります。どうしたら兄より多く釣れるか。いち早く浮いている個体を見つけるのはもちろんですが、ライギョは捕食が得意ではなく、エサのカエルをうまく捕らえられないことがよくありました。
そこで私は考えました。捕まえたカエルの足を少し引っ張って裂いて動きを鈍らせ、ハリに刺すのです。残酷だと思うものの、効果はてきめんでした。しかし、やりすぎて動きが鈍くなりすぎると、ライギョは興味を失います。そうなったカエルをハリから外して元のあぜ道に放したところ、周りから同じくらいの大きさのカエルがわらわらと集まり、弱った一匹に襲いかかるではありませんか。ついさっきまで一緒に跳ねていた仲間が、弱った途端に牙を剥く。私はその光景に息を呑み、しばらく動けませんでした。自然の厳しさというものを、あのとき初めて突きつけられたのです。
-Nov-25-2025-02-47-33-6004-AM.jpg?width=1280&height=720&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-25-2025-02-47-33-6004-AM.jpg)
痛みを知らない子どもたち
カエルだけではありません。水辺では、あらゆる生き物が命を奪い合っていました。コオロギはカエルに食べられ、カエルはヘビに飲み込まれ、ヘビは鳥にさらわれる。ヤゴがオタマジャクシを捕らえ、ザリガニがクチボソを挟み、サギがライギョを丸呑みにする。水辺にいれば、そうした生々しい命のやり取りに、否応なく出会います。
一方、今の子どもたちはどうでしょうか。水辺はフェンスで囲われ、草むらはアスファルトに覆われ、「良い子は川に近づかない」という間違った教育がなされ、自然界の命の奪い合いを間近で見る機会は激減しました。
かつてNHKで放送されていた『野生の王国』では、ライオンやトラが獲物をむさぼる場面がしばしば映され、子どもたちはその生々しさに目を奪われていましたが、そうした映像も今はめっきり少なくなりました。さらに近年、子ども同士の競争を避ける教育が広がっています。徒競走で手をつないでゴールし、順位をつけない運動会。学習では比較を避ける絶対評価や、自由進度学習が導入される学校もあります。
親や大人が子どもを守るのは当たり前ですが、それが行き過ぎると「過保護」になります。フランスの思想家ルソーは、18世紀に著した『エミール』の中で、「親が子を守ろうとするあまり、かえって弱くしてしまう」と書いています。
「自然を観察するがいい。そして自然が示してくれる道を行くがいい。自然はたえず子どもに試練をあたえる。あらゆる試練によって子どもの体質をきたえる。苦痛とはどういうものかをはやくから子どもに教える。(中略)試練が終わると、子どもには力がついてくる。そして、自分の生命をもちいることができるようになると、生命の根はさらにしっかりしてくる。」と。
ルソーが言う〝自然〟とは、単なる環境ではなく、生命の理そのものです。自然は子どもを苦しめるために試練を与えるのではありません。生きる力を授けるために、あえて痛みを与える――その厳しさの奥には、深い慈しみがあります。だからこそ、苦しみを遠ざける教育は、子どもの根を浅くしてしまうのです。 自然の厳しさと出会える機会が驚くほど少なくなった現代の子どもたちにとって釣りは、その感覚を取り戻す数少ない手段だと思います。「かわいい子には旅をさせよう」と言いますが、「かわいい子には釣りをさせよう」と心から私は思います。
大ヒット魚料理レシピ本に秘められたメッセージ
6万部を超えるベストセラーとなった『お魚イラストレシピ大百科』の著者・大垣友紀惠さんは、千葉県市川市出身のグラフィックデザイナーであり、アートディレクターでもあります。幼い頃、釣り好きの父親が釣りから帰ってくると、クーラーボックスの中を覗くのが何よりの楽しみだったそうです。
銀色に輝く魚たちの姿に、幼い心は強く惹かれ、その美しさこそが魚の世界への入口となりました。小学6年生の時には、ANAの特別塗装機「マリンジャンボ」のデザイン公募で最優秀賞を受賞。天才少女と呼ばれて脚光を浴び、その後デザインの道を歩み続けます。
2022年に刊行された『お魚イラストレシピ大百科』は国内外で高く評価され、英国のデザイン賞「D&AD Awards 2023」ではブックデザイン部門で〝Wood Pencil〟を受賞。アートとしての完成度が国際的にも認められました。 私がこの本のゲラを初めて手にしたとき、まずイラストの見事さに息を呑みました。
けれど、それ以上に胸を打たれたのは、ページのすみずみに宿る魚への愛情です。ウロコも皮も骨も内臓も――ふだんなら捨ててしまう部分を余すところなく料理に生かす。その姿勢は、押しつけではなく、ただ自然に「生き物とともに生きる」という感覚を伝えていました。
その瞬間、私の脳裏に『輪廻』という二文字が浮かびました。そして、まったく異なる分野ながら、近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』に通じるものを感じたのです。
近藤さんは、使わなくなった物にも命が宿っていると考え、「ありがとう」と感謝して手放す。その思想は、日本的なアニミズムや仏教的な輪廻観とも通じ、モノの命が次の形へめぐっていくという感覚の上に成り立っています。大垣さんのレシピにも、まさに同じ精神が流れています。料理を作るという行為を超えて、命をめぐらせるという祈りがあるのです。
料理本は毎年、数え切れないほど出版されます。しかし、その多くが消えていく中で、魚料理の本が6万部を超えるヒットとなったのは、単にイラストの美しさだけではありません。そこに込められた命への敬意、魚への愛情が、読者に届いたからだと私は思います。 食卓に並ぶ一皿の魚。その前で自然と「いただきます」と言葉がこぼれる。それは、命の循環を感じ取った者だけが持つ、静かな祈りなのです。

SDGsより「もったいない」
5~6年前のことです。ある大企業のトップと釣りに行ったとき、船の上でこんな話をうかがいました。
「最近、『御社はSDGsに関して、どのような取り組みをしていますか』と営業に来る人が増えましたが、ぼくはあの七色のバッジをスーツに付けている人は信用しませんね。彼らの言うSDGsを聞いていると、結局、金儲けでしかないんですよね。自然への愛が全く感じられない。生きた魚をまともに掴んだことがない連中がSDGsとか言っても、全然伝わってこないですよ(笑)」とその方はおっしゃっていました。
オフレコとは言え、そのようなことを直接聞くことができて、私は胸がすく思いがしました。 もちろん、私は地球や未来のために行動するという理念そのものを否定するつもりはありません。しかし、SDGsという言葉の背後にある「人間が自然を管理し、持続させる」という発想に、どこか違和感を覚えるのです。まるで自然が人間の手の中にあるかのような傲慢さを感じるのです。
日本には、はるか昔から「いただきます」や「もったいない」という美しい言葉が受け継がれてきました。その中には、自然の恵みに対する感謝、命への敬意、そして自らを自然の一部として見つめる謙虚な心が息づいています。日本人は、何かを支配するのではなく、共に生きることを選んできた民族です。
「いただきます」は、命をいただく痛みを感謝へと昇華させる言葉。 「もったいない」は、ものに宿る命や労力を無駄にしないという誓い。 これらは単なるスローガンではなく、生活の中に深く根づいた祈りの言葉です。
そんな文化を持つ日本人にとって、「SDGs」という言葉はどこか空虚に響きます。西洋がようやく持続可能性を掲げ始めたとき、日本ではすでに何百年も前から、自然と人との調和を大切にする生き方が続いていたのです。一方で、私は思います。SDGsの理念も、「いただきます」や「もったいない」の精神も、自然への愛慕に根ざしていなければ、ただの空疎な言葉になってしまうのではないでしょうか。
-Nov-25-2025-02-48-01-2646-AM.jpg?width=1280&height=720&name=07%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-25-2025-02-48-01-2646-AM.jpg)
「かわいい子には釣りをさせよう」
今、子どもたちは自然と触れ合う機会をほとんど失っています。食べ物がどこから来ているのか、命がどのように循環しているのか、それを実感できないまま成長しています。ハンバーガーやトロの握りが、かつてどんな姿で生きていたのかを知らない子がいる。もはや誇張ではなく、現実です。だからこそ、自然に触れる体験を取り戻さなければなりません。
釣りは、その最もシンプルで、最も深い方法のひとつです。自然の中で魚と向き合い、命を奪う責任を自らの手で引き受ける体験。それは「生きるとは何か」を全身で学ぶ時間です。釣りあげた魚の目の輝き、息づかい、そして命が静かに消えていく瞬間。そのすべてが、言葉を超えて教えてくれます。魚を食べるとき、「いただきます」という言葉が単なる習慣ではなく、祈りとなるのです。 自然に触れず、命に触れずして、持続可能性を語ることなどできません。 だから、私は思うのです。かわいい子には釣りをさせよう、と。

%20(2).jpg)


%20(2).jpg)
%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

.jpg)
a.jpg)
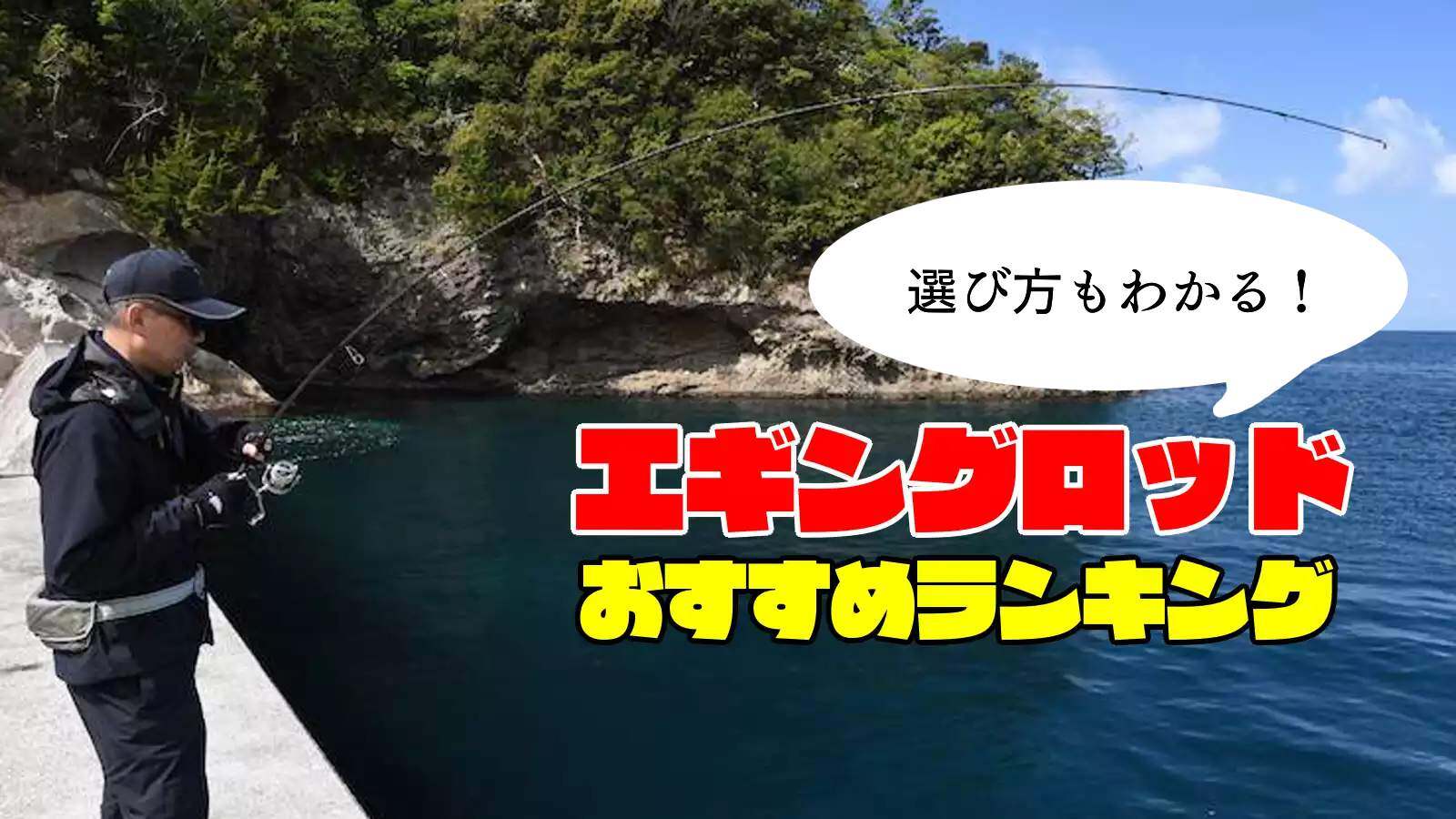
.jpg)
.jpg)
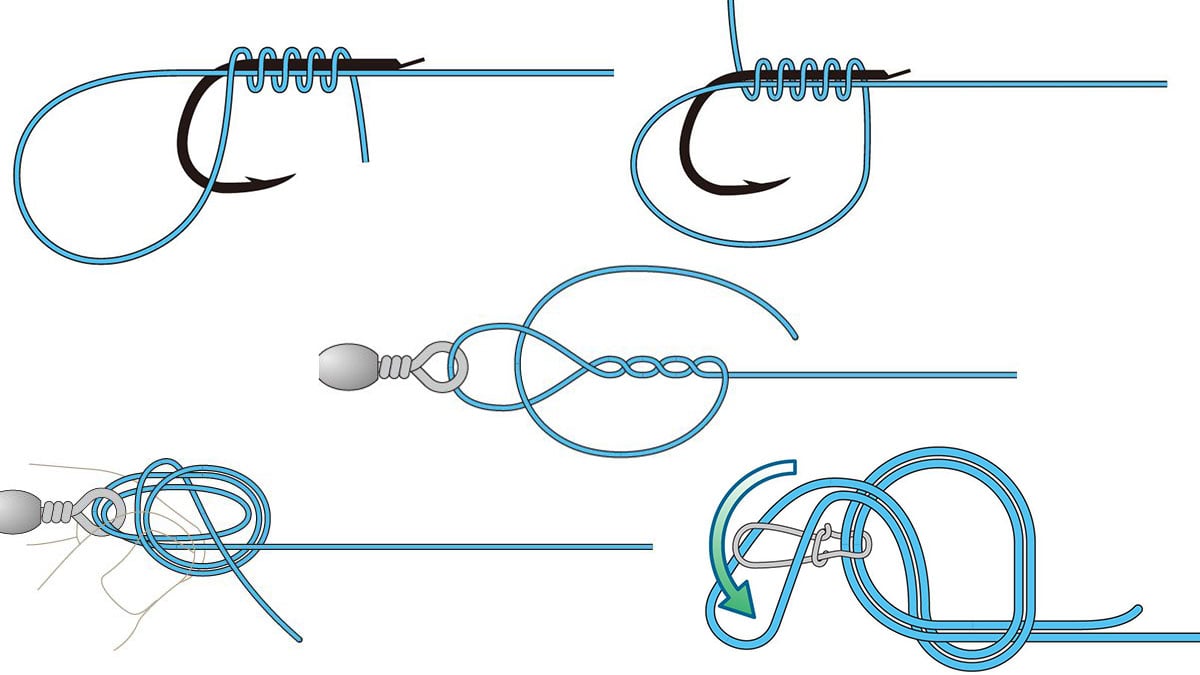
.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.webp?width=360&height=120&name=bac2025-1024x183%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).webp)

.jpg)


