エギングを始めたいあなたへ贈る入門ガイド。アオリイカの生態から、秋と春のシーズンの違い、餌木の選び方、そして堤防・磯・サーフといった場所別の釣り方まで。エキスパートがゼロから徹底解説します。
エギングを始めたいあなたへ贈る入門ガイド。アオリイカの生態から、秋と春のシーズンの違い、餌木の選び方、そして堤防・磯・サーフといった場所別の釣り方まで。エキスパートがゼロから徹底解説。
まとめ◎編集部
写真&文◎新保明弘
新保明弘プロフィール:昭和52年生まれ。静岡県在住。伊豆半島から御前崎までをホームグラウンドにする。オフショア、ショアともにルアーフィッシングならば何でもこなすが、特にエギング、シーバス、メバル、回遊魚の釣りが得意。
アオリイカは岸からねらえるイカの代表格
イカといえば誰もが大好物。また、日本人はイカを釣ることが大好きである。漁火に例えられるように、イカは船の沖釣りでなければ釣れないイメージが強い。私も釣りをしない職場の仲間とイカの話をすると、「えっ、岸から釣れるんですか?」と問い返されることも多い。
確かに多くのイカが沖釣りの対象とされるが、海のルアー釣りのジャンルとして紹介するアオリイカは、古くから岸釣りの対象として楽しまれてきた代表格である。食味からもファンが多いのはうなずけるが、アオリイカはその名のとおり、大きなエンペラが生み出す推進力が強く、釣り味、引きを楽しめるイカとしても人気が高い。

本州の中部以南が主な生息域
アオリイカは本州、北海道以南の沿岸に分布し、特に太平洋側では茨城県沿岸より南、日本海側では福井県の西側以南に多いとされる南方系のイカである。地方によって、ミズイカ、バショウイカとも呼ばれ、一般によく知られているスルメイカ、ヤリイカよりも沿岸性が強い。
産卵期は、南へ行けば行くほど年明け後の早春とされるが、昨今は黒潮の影響の変化、日本近海の海水温の変化に伴い、日本沿岸の生息域の範囲内で年明けから7月までと幅が広がっているのが現状である。
8月頃から港周りの穏やかな水域で、群れをなした幼いイカが確認されるようになる。イカ類のほとんどは1年から1年強で成長し、その過程で産卵行動を行なうため成長が早い。アオリイカも例外ではなく、寿命を全うするまでに大きなものは3kg以上に達する。
そもそもエギングとは?
アオリイカを岸からねらうには、古くはアジなどの生きエサを利用した泳がせ釣りが行なわれてきた。そのため、玄人向けの釣りとして手軽なイメージではなかった。ところが近年、絶大な人気を誇るエギングの誕生により、多くの人がその存在を知り、海のルアー釣りの入門として選択できるほど身近な存在となっている。
エギングで使用するルアーの一種が「餌木」である。餌の木と書くように、古くは主に楠くすのき、木を材料として作られた日本古来からの漁具が進化したものが、エギングで使われる餌木である。
餌木は古くは船で行なわれる漁、沖釣りで用いられてきた。主に小型の船舶で餌木をゆっくりと引っ張りながら、大きくシャクリ上げてアオリイカを誘うスタイルだった。
やがてロッドとリールが進歩してくると、岸からでも遠くのポイントを餌木で探れるようになってくる。さらに、伸びの少ないPEラインが開発されてからは、イカ釣りに重要なシャクリといわれるアクションの効果が強くなったことが、岸からのエギングの釣果を大きく飛躍させるきっかけとなった。シャクリをどのように、どのタイミングで入れるのか、それが釣果に影響してくる。

エギングのシーズンは春と秋がメイン
アオリイカの醍醐味といえば、昔から変わらず1kgを超える春の大型ねらいである。しかし、近年はエギングの人気とともに、アオリイカは通年のターゲットとして認識されるようになってきている。
秋の数釣りシーズンは入門に最適
入門者がエギングを始めるタイミングとしてお勧めなのは、9月後半~11月だ。春から初夏にかけて孵化したアオリイカの新子が、手の平大の大きさ、通称「ボタモチ」と呼ばれる200~500gに成長したものをねらうシーズンである。
前にも記したとおりアオリイカは成長が早い。1年ほどで3kg以上に成長するには、盛んに捕食活動をしなければならない。昼夜を問わず活発にエサを追うことから、当然、餌木に対する反応もよいのである。
エギングの醍醐味の1つにサイトフィッシング(アクションさせる餌木とアオリイカを見ながらの釣り)がある。港や穏やかな堤防周りで、餌木を追ってくるアオリイカが高確率で確認できるのもこのシーズン。サイトフィッシングでは、アオリイカが餌木のシャクリ、アクションに対してどう反応するか、餌木を抱く(イカが餌木をとらえること)のかを観察することができる。これは深場をねらう時のイメージにも最適といえる。
秋のエギアクション
秋は活発に捕食し好奇心が強いアオリイカに餌木の存在をアピールするために、シャクリやアクションを激しく行なう。力みすぎるのもよくないが、ロッドが風を切るように強くアクションを入れると、よりアピールできる。まだ、警戒心の弱い小型は水面に向かう餌木を追って自らも水面近くまで浮いてくるので、シーズンの初期は餌木を表層まで探るのが基本。ただし、シーズンが進んで大きくなると警戒心は増し、上に向かう餌木に対しては距離を置くようになる。

簡単には釣れないからこそ面白い、春の大型シーズン
エギングファンが常に目標とする1kg超え。早生まれの個体は11月後半に1kgに達するものもいる。しかしより高確率で大型を求めるなら年明けの1月以降である。ただし、その頃になると、水温低下とともにアオリイカの活性も低下傾向となる。また、越冬のため水深30mほどの深場、沖合に出る傾向もあり、物理的に釣りにくくなる面もある。
そんな厳寒期を少し我慢して3月に入ると、海水温の上昇とともにアオリイカは産卵行動をとり始め、大潮回りを基準に接岸する。釣り人にねらわれ続けた秋シーズンを乗り越えて1kg以上に成長したアオリイカは、警戒心が増していることはいうまでもない。秋と同じ釣り方をしていては、釣果にたどり着くことが難しくなる。時合、ポイント選びやシャクリ方など、餌木のアクションもより考慮しなければならないシーズンでもある。
春のエギアクション
産卵を控えた春の大型アオリイカは、体力を温存するため、エサを積極的に追いかけず、楽に捕食できるものを選ぶ傾向にある。
そのため、釣り方としては、まず激しいアクションでエギの存在を気付かせ、興味を引く点は秋と変わりない。しかし、そこからが大きく異なる。重要なのは、アクションとアクションの合間に、エギをしっかりとイカに見せ、「抱く間」を十分に与えることだ。
また、移動距離を抑えた小さいシャクリや、海底でエギを静止させる「ボトムステイ」といった、ソフトな誘いが効果的な場面も多い。
.jpg?width=1200&height=900&name=95165-1%20(2).jpg)
餌木の基礎知識と選び方
餌木は他の海のルアーとは全く異なる特性を持っており、大きさも独自の号数で表記される。まず動き、アクションである。ほとんどのルアーは、リールを巻くことで体をくねらせたり、震わせたりとアクションする。ところが餌木は早く引いても、遅く引いても全くアクションしない。引かれた方向に向かって真っ直ぐ進むだけである。
そして必ず沈む。頭を少し前に倒した状態で一定の姿勢を保ち、沈んでいく。これだけでは全くエサとは思えない動きであるが、ロッド操作によってシャクリ、ダートなどのアクションを加えることで生命感が生まれる。この動きと一定の姿勢が合わさることで、イカが餌木を抱くのである。イカが餌木を抱く瞬間のほとんどは、餌木が一定の姿勢を保ちながらゆっくり沈下、もしくは静止している時である。

餌木の大きさ、重さ、タイプ別の沈下速度について
餌木は号数が大きくなるほど重さもサイズも上がる。一般的に広く使われているのは3.5号で、ハリ(カンナ)の部分を除いた長さが10.5cm、重さは20g前後。0.5号刻みで長さは1.5cm、重さは5g程度の差が出てくる。たとえば3.0号=9.0cmで15g、3.5号=10.5cmで20g、4.0号=12.0cmで25g、となる。また、現在のエギングの餌木は号数以外にシャロー(S)、ノーマル、ディープタイプ(D)と沈下速度が異なるタイプに分かれていることがほとんどである。
餌木の使い分け
それではどのように餌木を使い分けていくかである。まず大きさだが、号数が小さいほど小型のアオリイカが、大きくなれば大型が抱きやすくなる傾向がある。秋の数釣りシーズンには3.0号を基本とし、春から初夏に1kgアップをねらうのなら4.0号を多用する。
シャロータイプは沈下速度がよりゆっくりなので、海底が目視できるような浅場ねらいに選択する。また、アクションの間をより長く取るために使用する場合もある。ディープタイプはその名のとおり、深場でしっかりと餌木を底まで沈めてねらう。潮の流れが速いポイントや、より飛距離を出したい時にも用いられる。
しかし、基本的には3.5号のノーマルタイプの餌木でこと足りる。最初からあまりタイプを気にすることは、お勧めできない。ロッドへの抵抗や、餌木までの距離感などがある程度つかめるようになってから使い分けを考えたい。強いていえば、ディープタイプは根掛かりが多いので、はじめはシャロータイプから使うようにするとよい。
.jpg?width=1200&height=674&name=3-Dec-23-2021-07-35-46-16-AM%20(2).jpg)
ポイント別の釣り方&タックル
ここからはポイント別に、釣り方や場所選びのコツ、最適なタックルなどを解説していく。
堤防でのエギング
港や防波堤周りは足場がよく入門者が釣りやすいポイント。秋の数釣りシーズンは、足元の船陰やロープ周りに新子の群れが見られることもある。港内に大型船や生けすが係留、設置されている大規模な港は1年を通じてねらえる。そのほかポイントの目安として小メジナ、メバル、アジがいればかなりの確率でアオリイカにも出会える。
港や防波堤周りをねらう場合、ロッドは8ftクラスを中心に選択するが、足場が高かったり、大きな港の出入り口など潮通しがよいポイントをねらうのであれば、9ftクラスを選択する。ボタモチサイズをサイトフィッシングでねらう場合は、2.5~3.0号の小さめの餌木を激しくアクションさせると反応がよい。イカの目の前に餌木を落としたくなるが、沖へキャストしてから近づけるように餌木を操作する。この時、多少スレている個体は一定の距離を保ち、近づいてこないことがある。その場合はさらに餌木のサイズを下げる、カラーを変えるなども手だが、海底が見えていれば、アクション、シャクリ後に餌木を底まで沈めて静止させると抱いてくることもある。
春から初夏の大型シーズンは、潮通しのよいポイントをメインに選択する。港の出入り口付近や、防波堤であれば先端部付近がよい。ポイントはその規模が大きいほどよいとされるが、規模が小さく底が見えるようなポイントでも、マヅメ時には充分にチャンスがある。
また、港内のちょっとしたスロープ周りや、船溜まりでも大型のチャンスがある。春から初夏にかけて産卵行動のため浅場に来る大型のアオリイカは主に海藻の周りに産卵するが、港内の生けすを支えるロープや、船を支えるロープのアンカー周りなどに産卵することもある。大潮回りや大潮後の中潮回りでは、港内にメスの回遊を待つ大型のオスが入っていることもある。潮通しがよいポイントが混雑して入りにくい場合でも、あきらめず港内をていねいに探ると思わぬ大型の釣果に恵まれることがあることを覚えておくとよい。

大型攻略のコツとしては、餌木のサイズは3.5号以上を使用し、シャクリ、アクションの間を長めにとることで餌木の不要な浮き上がりを防ぐ。普段の間の取り方でアクション、シャクリを入れたくなっても、そこから5秒、10秒と長くポーズを取るように意識する。秋は釣れたのに春になかなか釣果が伸びない、そんな悩みに直面した時はぜひこれらのことも試してみてほしい。
秋の小型アオリイカは非常に餌木に対する反応がよいが、少し慣れてきたらいたずらに釣りすぎず、大きくなるまで待つ余裕を持ちたい。また、3.5号以上の餌木を使い、胴長が餌木以下のサイズはリリース、キープは1日3杯までとするなど、自分でルールを決めるのもよい。釣り場によっては、釣り人にアオリイカの保護を求めている箇所もあるので、しっかりと守るよう心掛けたい。

磯でのエギング
磯もエギングに最適なフィールドである。港などとは異なり、アクセスのしにくさ、根掛かりなどのトラブルも起きやすいため、釣り人は少なくアオリイカがスレていない傾向がある。ねらい方のコツをつかめば、入れ食い、夢の大ものの可能性も高くなる。
タックルは足場や打ち寄せる波を考慮する。時には沖にある沈み根周りをねらうため、9ftクラスの長めのエギングロッドを使用する。ラインシステムは根ズレによる傷を考慮して、PEライン1.0号、ショックリーダーは3.0号と太めを使用するとよい。安全対策もしっかり行なう。フローティングベストは固定式を選択し、足もとはスパイクブーツを着用する。
根掛かりを避けるため、表層から中層をねらう
磯のエギングでは根掛かりが付きまとう。餌木はアクションだけでなく、沈めることでアオリイカにアピールするが、磯で無暗に餌木を沈めると間違いなく根掛かりしてしまう。特に、沈み根が確認できるような比較的浅い磯ではなおさらである。
初めての磯に入る際は、可能であれば干潮の下げ止まりを選び、少しでも地形を確認、把握してから餌木をキャストする。さらに、はじめは表層から中層をメインにねらうようにする。キャストした餌木が着水したら、5~10秒でシャクり、アクションに入る。アクションとアクションの間も、春の大型のシーズンであっても秋イカをねらう感覚で短めにする。磯のアオリイカはスレていないことが多く、速いテンポでねらっても充分に釣れる。そうすることで根掛かりを少なくすることができる。
ただし、昨今のエギングブームで釣り人が多いポイントでは簡単に餌木を抱いてくれないことがある。そんな時には根掛かり覚悟で、しっかりと間を取る必要が出てくる。この場合、沈下速度の遅い、シャロータイプの餌木を使用するとよい。沈下速度が遅いぶん、間を5秒程度長く取ることが可能。また、沈めている段階で根に触れても、浮力が強いため、ノーマルやディープタイプよりも根掛かりが少ない。
r.jpg?width=1200&height=675&name=5-Dec-23-2021-07-57-24-22-AM%20(2)r.jpg)
潮通しのよい岬状の磯も好ポイント
岬状になった磯は特に潮通しがよく、好ポイントである。ここでは潮の流れが速い時に、ディープタイプの餌木を使用する。基本的に水の流れは表層ほど速く、底に近くなるほど遅くなる。そのため、ディープタイプの餌木で表層を早く通過させるようにするためだ。
ディープタイプの餌木を使用してもアッという間に流されてしまうような状況の時は、潮変わりを待つ。上げから下げ、下げから上げに変わる時に、流れが止まる時間が必ずある。潮の大きさ、風向きなどによって止まっている時間は変化するが、その時のチャンスは大きい。強い流れを避けて根の陰に潜んでいた、もしくは沖に出ていたアオリイカが一斉に射程圏内に接岸してくる。こんな時には複数で釣りをしていて全員に同時に乗ることもある。
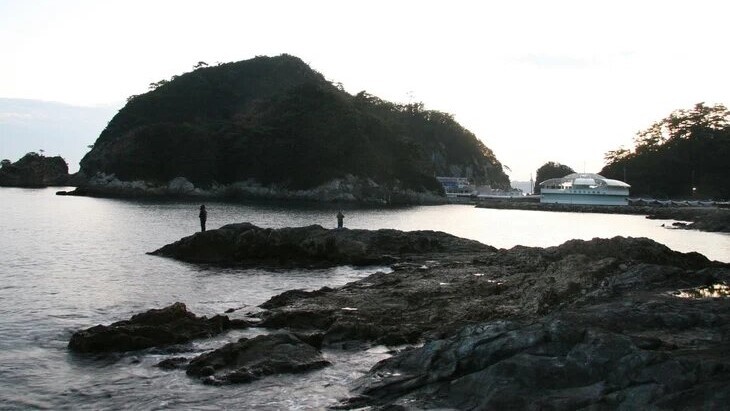
サーフ・ゴロタ場のエギング
イカといえば水深が深くないと釣れないイメージが強い。しかし沿岸性のアオリイカは、成長のための捕食活動で遠浅のサーフ(砂浜)や、玉石で形成されるゴロタ場にもエサを求めて接岸してくる。とはいっても、やはり極端な遠浅ではなく、ある程度急深なポイントがよい。
そのほかの目安としては、イナダやサバ、ソウダガツオなど青ものの回遊が見られるサーフやゴロタ場であればほぼ間違いなくねらえる。ちなみに、青ものはアオリイカの天敵。青ものが盛んにエサを追い求め、ナブラを立てているような時に同時にねらうことはできないが、青ものの時合が過ぎたタイミングや、異なるシーズンにはそれが可能になる。
.jpg?width=1200&height=674&name=6-Dec-23-2021-08-01-49-84-AM%20(2).jpg)
広大なサーフやゴロタでポイントを絞る目安とは
サーフ、ゴロタ場がなんといってもよいのは、混雑と無縁であること。最近はこうした場所もポイントとして認識され、釣り人は見られるが入れないほどの混雑はない。
はじめは広いポイントの中から、より可能性の高いスポットをいかに絞り込むかが重要だ。岬やワンド状などの地形変化はもちろん、潮目が形成される場所の正面を選ぶと、ベイトフィッシュが多く、アオリイカも接岸しやすい。明るい時間帯にポイントを遠くから見渡せる場所で、波の立ち方が変化している潮目を見つけておくとよい。
ベイトフィッシュが多い時は日中でも可能性があるが、基本的にはベイトフィッシュが接岸しやすいマヅメ時がチャンス。さらに、青ものの回遊が見られる時期は、より夜行性であるアオリイカの習性を意識してマヅメ時でも朝マヅメならば青ものが回る前、夕マヅメは青ものが去った後と、暗いタイミングでポイントに入るようにする。

基本はとにかくロングキャスト
サーフ、ゴロタ場では、とにかくロングキャストが有効。ベイトをねらってアオリイカが波打ち際まで寄っていることもあるが、ほとんどはカケアガリよりも沖にいることが多い。そのため、ロッドも8ft中盤から9ftほどのやや長さのあるロッドが使いやすい。また遠投しやすい重めの餌木をメインに使用するので、Mクラスなどのパワーのあるロッドが最適だ。
釣り方としてはロングキャストしたら、水深に合わせて5~30秒沈め、シャクり、アクションに入る。この時、シャクる前に必ずラインを張ってアオリイカの重みを確認する。この動作はどのポイントでも行なうことを勧める。特にサーフ、ゴロタ場では、アオリイカは捕食活動で接岸しているので、最初のフォールで餌木を抱いていることも少なくない。
大きくシャクり、アクションを入れたらふたたびフォール。水深が浅い場合はスローリトリーブか、ロッドの先を横に引く、サビくなどして餌木を横移動させる。この時にジンワリと重みが乗ればアタリである。なければ餌木が底に触れるまで繰り返す。
ゴロタ場では基本的に根掛かりが多いが、少ない場所では餌木が底に触れてもすぐ回収せず、10秒程度静止させる。あるいはコツコツ、ズルズルと底をカニがゆっくり歩くイメージでズル引く。餌木を追ってきたアオリイカはエサを追い詰めたと思うのか、大型や秋の後半シーズンほど、このタイミングで餌木を抱いてくることが多い。

※この記事は『海のルアー釣り入門』(新保明弘著)を再編集したものです


.jpg)
a-1.jpg)


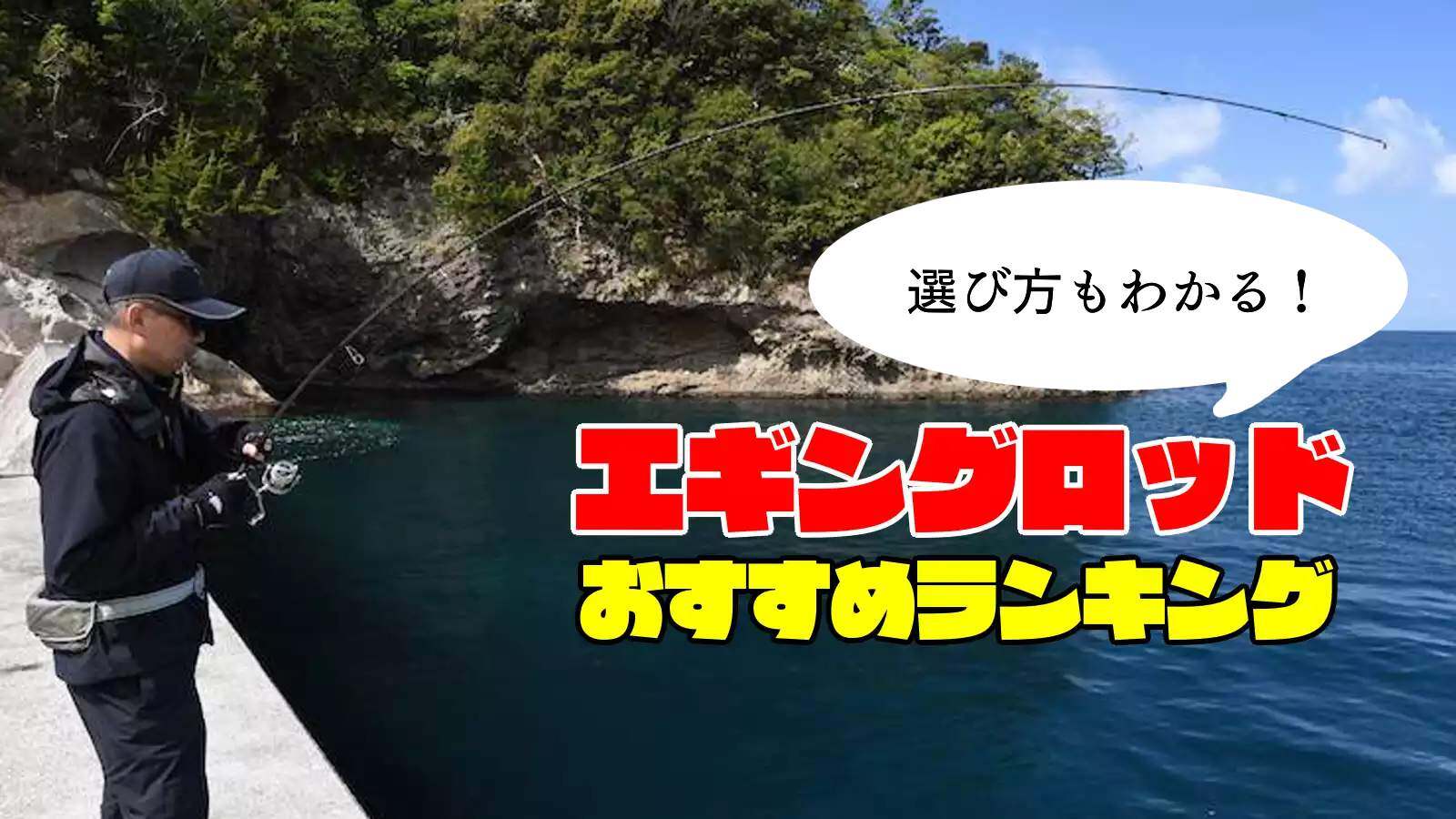


-1.jpg)




.jpg)
.jpg)
-1.jpg)
.jpg)
.jpg)





-1.jpg)
.jpg)

-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
-Feb-24-2026-08-47-39-9439-AM.jpg)

