市販のサケ釣り用のエサは種類が多く、どれを選べばよいか迷ってしまいがち。しかし、それぞれに適材適所があり、選び方しだいで釣果を左右する場合も。そんな悩みに釣具店スタッフが助言。
2024年からオホーツクの3市町では、サケ・マス釣りに関する新たなルールが策定された。末永くサケ釣りを楽しむため、釣り人なら厳守すべきだが、ルール導入後、釣り場はどう変わったのか。投げ釣り愛好者のベテランが導入前を振り返りながら、ルールに則った新たなスタイルを提案。
Photo & Text by Hideki Yokokawa(North Angler’s)
North Angler’sとは?:北海道での釣りを満喫するための情報誌。北海道の自然を体感するキャンプの情報や、フィールドを守るための環境問題にも光を当て、多角的な視点からアウトドアライフを提案している。誌面と連動したウェブサイト『つり人オンライン』での記事展開に加え、好評放送中の『ノースアングラーズTV』や公式動画チャンネルである『釣り人チャンネル』を通じても、北海道の釣りの魅力を発信している。
サケ・マス釣りはルール導入でどう変わった!?
2024年からオホーツクの3市町で、サケ・マス釣りの新たなルールが策定された。そのルールと、導入後どのように釣り場が変わったか振り返っていこう。
【場所取り禁止】【テント常設禁止】
オホーツク東部の人気ポイントである止別川や興部川に河口規制が設けられる以前、河口に近い優良ポイントを地元のグループなどが長期に渡り占有していた。テントを常設したり、車輌を常時置いたりして、他者を近づけない雰囲気が漂っていた。そして、サオ立てやロッドを広範囲に並べて「縄張り」をアピール。彼らは知り合いしか自分の縄張りに入れないことから、不平不満を訴える釣り人は少なくなかった。
こうした地元の事情を知らない釣り人が入ろうとすると、排除するために激しく口論するなどのトラブルが絶えなかった。
また、サオ立てやロッドを捨てられたり、盗まれたりするような事件も頻繁に起きていた。さらに、釣り禁止の内水面で平然と釣りをしたり、通称「ギャングバリ」で引っ掛け釣りをしたりする密漁者も後を絶たなかった。釣りをしない人たちにサケ釣りの楽しさより、“物騒でネガティブ”なイメージが強調されて伝わってしまうのは無理もなかった。
2018年の興部川と止別川に続き、2022年、ついに藻琴川にもサケ・マス採捕禁止区域と期間が設けられ、事実上、河口付近でのサケ・マス釣りが不可能になった。その後、地元のテント常設組は自然消滅し、長期間に渡る場所の占有者が減ったことで、釣り場でのトラブルは激減した。
【路上駐車・私有地侵入厳禁】【指定区域、期間の立入禁止】【迷惑駐車】
「関係者以外立入禁止と指定された場所」は、多くの漁港で明確化され、違反は厳格に取り締まるようになった。網走市の帽子岩を例にあげると、数年前までは規則を無視して入る釣り人と、取り締まる巡視員とのいたちごっこが続いていた。が、ルール施行後、立入禁止区域でサケ釣りをする釣り人の姿はほとんど見なくなった。
駐車スペースとして利用できていた「私有地」は年々、立入禁止箇所が増えている。ルールのないオホーツク中部や北部地区でも、近年は立入禁止の看板設置に加え、コンクリートブロックで完全に封鎖されたところも多い。
私有地の立入禁止区域に正当な理由なく侵入すると、刑法上の「住居侵入罪」(刑法第130条)や「軽犯罪法」違反となる。これらは逮捕や罰金など刑事罰の対象となり、前科がつく可能性もある。以下は、違反となるケース。所有者が警察を呼ぶと現行犯で検挙されることもあるので注意してほしい。
・立入禁止の看板や掲示を無視して敷地内に入ったり、許可なく立ち入ったりした場合。
・塀やフェンスで囲われているなど、外部から立ち入りを禁止していることが明確な場所に侵入した場合。
網走市は、釣り場のそばに「臨時駐車場」を設けているにもかかわらず、路上駐車や違法駐車は後を絶たないのが現状である。指定された駐車制限区域には水産加工場が多く、作業車やトラックの出入りが頻繁にある。路上駐車は慎み、タックルなどを降ろしたら速やかに臨時駐車場へ車輌を移動するなど、近隣住民の迷惑にならないようにしたい。
.jpg?width=1280&height=720&name=P067-071-A-03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
.jpg?width=675&height=900&name=P067-071-A-04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
【釣りザオは3本まで】【持ち帰りは3尾まで】
ルール施行以前、私は通常6本のロッドを使用していた。周りには10本以上並べる釣り人も珍しくなかった。大きな群れが入ったときは、ヒットしたサケと格闘している間にも、ほかのロッドは次々としなり始める。サケ釣りで最もアドレナリンが出る瞬間だ。使用しているドウヅキ仕掛けは、向こうアワセで掛かるように工夫している。そのため、アワセを入れなくてもバレる心配は少ない。しかし、放置時間が長ければ長いほど、ライン絡みのリスクは増す。滅多にない爆釣タイムだからこそ、絡んだラインを解いている余裕はない。
そこで、トラブルが生じたロッドについては、邪魔にならないように仕掛けを上げたまま放置。稼働しているロッドのみで、釣りあげては投げ返す、いわゆる「手返し優先」の数釣りに夢中になる。短いラッシュアワーが終わり、一息ついたときにいつも思うのは、「同時に扱えるロッドは3本が限界では?」だった。
2023年、偶然にもルール策定のための調査が始まったことを知った。私も参加した斜里町のアンケートでは、とくに「サオ数」と「キープ尾数」の項目が目にとまった。ルール策定の趣旨は「資源保護」ということが分かったので、前倒しで
(1)ロッド2本
(2)サケのキープは5尾(それ以上はリリース)
(3)釣った魚は自分用(他人の分は釣らない)
という“マイ・ルール”を決めて、友人とともに検証することにした。
マイ・ルールをワンシーズン試行して分かったことはいくつかある。まず、ロッドの数は釣果に影響しないこと。6本だから釣れるとか、2本だから釣れないということはない。次に、投げ釣りの三大要素「エサ・投げ・仕掛け」が釣果に直結することをあらためて確認できたのも大きかった。
さらに、新たなオリジナル仕掛けの開発を強いられたことも楽しかった。使えるフロートルアーが限られることで、ドウヅキ仕掛けを工夫しなければならないからだ。また、省エサ効果により財布にやさしいこともメリット。そして、ロッド2本だとエサ替えが面倒だと感じなくなった。ハリからエサがなくなる前に替えると、常に新鮮なエサで魚を誘うことができる。定数をキープしたら撤収と考えると、エサ替えを頻繁に行なっても消費量は激減する。
ほかに、準備と撤収に時間をかけずに済むことも挙げられる。ラインなど消耗品の大幅なコストダウンになり、タックルの大幅な軽量化にもつながる。サケ釣りの醍醐味は、ロッドの数に比例して大きくなるわけではないことを学んだ。
.jpg?width=1012&height=900&name=P067-071-A-05r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
ルールの施行とスタイルの変化
2024年。満を持して、斜里町・小清水町・網走市が『海浜サケ・マス釣りルール』を施行した。リリースを認めないこと(網走市)以外、すべて統一されている。小清水町と網走市のサーフで釣りをしていた人たちは、私の想像以上にルールを意識し、守ろうとしているように見えた。シーズンをとおして釣るうちに、成果だけではなく、課題や改善点もみえてきたが、ルールが施行された初年度である。サーフを訪れる釣り人の意識はしだいに高まっていくはずだ。
地方自治体と漁業協同組合、警察など関係機関の連携・協力のもと、釣り場の正常化に向けた啓蒙活動や巡視活動が地道に行なわれてきた。同時に、釣り場から場所取りの杭やロープ、物品の撤去を実施。当初は釣り人とのイタチごっこだったが、ルールが施行された現在、ほぼ皆無となった。
ルールの遵守がサケ釣りの敷居を下げることにつながり、ビギナーもベテランも安心して最大限に楽しむことができないだろうか。ルールの範囲内でどのように楽しめるのか、私なりの提案をいくつか紹介したい。
まず、6本ロッド時代に比べて、タックル総量が約半分に減った恩恵は思いがけないほど大きかった。準備や撤収にかかる時間を大幅に短縮することは、戦術面でかなりのアドバンテージになる。たとえば、時合(じあい)を目がけた短時間勝負の場合、準備を時短して、釣りにかける時間を充分確保できるようになった。撤収直前まで残しておいた1本ロッドにヒットするシーンも増えた。
また、入ったポイントが不発でも、素早くポイントを移動できるのもよい。移動した先で爆釣があるのがサケ釣り。スリリングな釣りを堪能できるようになったことは歓迎すべき要素だ。
%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=896&height=504&name=P067-071-A-14a%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
シェアで楽しく場所キープ
釣り場に着くと、まずは波やサーフのようすを観察して、入るポイントを絞り込む。とくに、離岸流の両サイドには、魚が付くカケアガリができるので、ポイントとして信頼している。
沖を眺めると、両サイドは波が立っているのに、波が立たないところがある。よく見ると、そこだけ海の色が異なり、沖に向かってライン状に伸びている。それが沖に向かって海水が払い出される離岸流である。ビギナーは少し高い位置から観察すると、より分かりやすいかもしれない。
離岸流を見つけたら、その両サイドの白波が立つ位置が、ターゲットとなるカケアガリだ。カケアガリの正面に釣り座を構えることができれば、釣果は期待してよいだろう。離岸流が発生する近くの砂浜には、貝殻やゴミが溜まっている。それを目印に探してもよい。
サーフが空いていて、自分が先行者となる場合は、隣とのスペース(すき間)を広めにキープするようにしている。ロッドの間隔は、自分の歩幅で7歩と決めているので、どこでも同じ条件で釣り座を設営できる。あとから来た釣り人(後着者)を拒まずに、すき間に入ってもらうのも、お互い気持ちよく釣りをするためのマナーであると考えている。
自分が後着者となる場合は、先行者のすき間を歩幅で測り、入れるかどうかの判断をする。そのためには、日頃から歩幅でロッド間の距離を把握しておくことが大事。入れると判断したら、必ず両サイドの先行者に挨拶をするなどしてコミュニケーションを試みよう。「先行者が優先」は、釣りの世界では常識。先行者が気を遣ってロッド間隔を詰めることがないように配慮し、すき間が狭い場合は自分のロッドを減らすようにする。
定数をキープしたら、早上がりをして、釣り場に長く居座らないのもルール下では提案したい。「ヒット・アンド・アウェイ」(釣ったら、釣り場を離れる)の気持ちをもとう。私は以前から、釣り場が最も混んでにぎわう朝マヅメを避け、明るくなってからサーフに行き、楽々場所をキープしていた。勝手に「出待ち」と呼んでいるが、朝マヅメを打ったら帰る地元勢の後ろでのんびりと待ち、空いたタイミングで場所をキープする方法だ。トラブルやストレスなく場所をキープできる平和的手段であり、帰る地元のベテランと顔見知りになれば、最新の釣り情報もシェアできるのがありがたい。
「釣り場のシェア」は、ベテランはもちろん、これからサケ釣りを学びたいビギナーにもメリットが大きい。場所と情報を気持ちよくシェアしながら、それぞれのサケ釣りを思う存分満喫したい(そんな雰囲気のサーフになったらいいなと思いませんか?)。
.jpg?width=1280&height=720&name=P067-071-A-15%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
サケ釣りの時合はいつなのか?
サケ釣りにおいて、朝マヅメがよく釣れるのは知られている。しかし、朝マヅメ以外でも時合を読めば、サケを釣ることはできる。時合とは、魚の活性が上がり、食いがよくなる時間帯のことを指す。「沿岸のサケは捕食しないから関係ない」と思う釣り人は、もはやいないだろう。なぜなら、エサを付けたほうが圧倒的に食いがよくなることを知っているからだ。では、時合はいつなのか?
時合は、潮の満ち引きを調べて、潮が動く時間帯を予測すれば知ることができる。干潮から満潮になるまでを10等分したうちの干潮0分(ぶ)から数えて3分まで満ちると、「上げ3分」の始まりになる。そこから7分まで潮が満ちていく間が、潮が最も動く時合になる。逆に、満潮から干潮になるまでを10等分したうちの干潮0分から数えて7分まで潮が引くと、「下げ7分」の始まりになる。そこから3分まで潮が引く間が、潮が最も動く時合になる。いうまでもなく、大潮や中潮の時合は激アツ。時合をねらい打ちすれば、日中でも関係なくサケは釣れるのだ。
一方、干潮前後(3分~0分~3分)と、満潮前後(7分~10分~7分)は「潮止まり」と呼ばれ、潮が動かず魚の活性は下がる。私の場合、潮止まりのときはリラックスして食事をしたりして時合の20分前を待つ。20分前になると、投げていた仕掛けを回収。天候や海の色を考慮してマッチしたフロートルアーに交換したり、エサ替えをして投げ返す。時合の開始時刻には、新鮮なエサを付けたフロートルアーがサケの目の前を泳いでいるイメージだ。
最後に、この機会に3市町を移動しながら釣りを楽しむことを提案したい。いつもと異なる風景を眺めながら、新鮮な気持ちで新たなフィールドを攻略する……。その途中、各市町の観光もプラス。温泉にグルメ、宿、キャンプ等々。そうすれば、釣行の充実度が増すのではないだろうか。
.jpg?width=1280&height=720&name=P067-071-A-17%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
※このページは『 North Angler’s 2025年秋号』に掲載した記事を再編集したものです。

a.jpg)
%20(2)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)








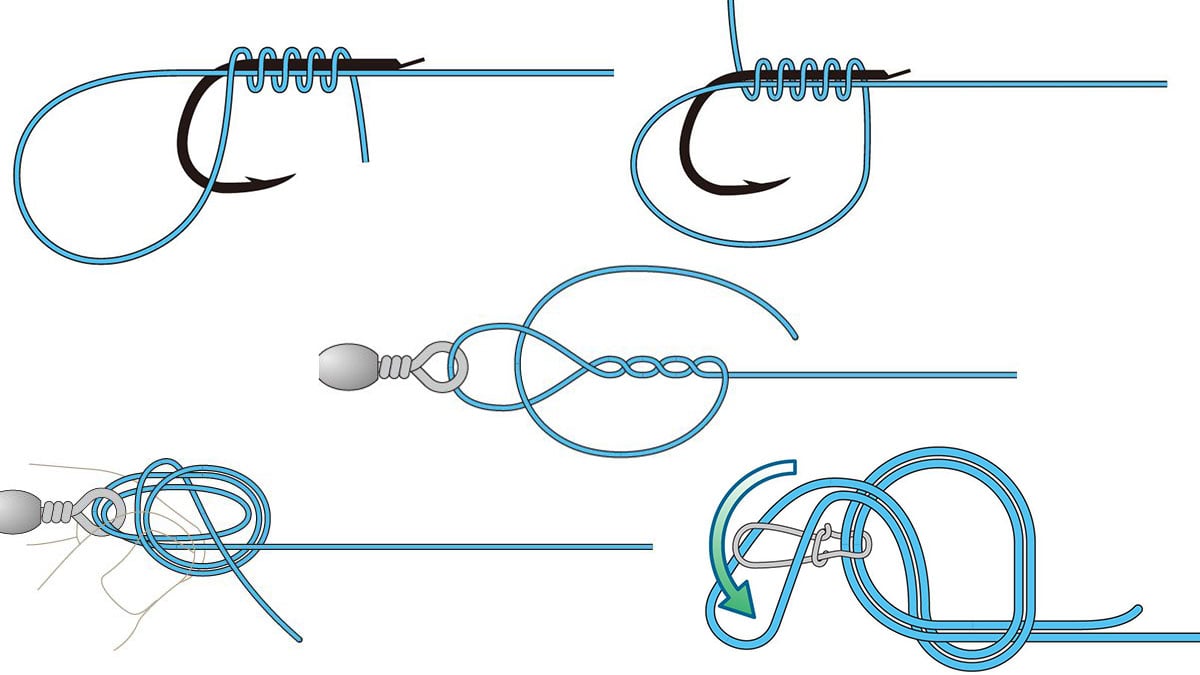


%20(2).jpg)

%20(2).jpg)







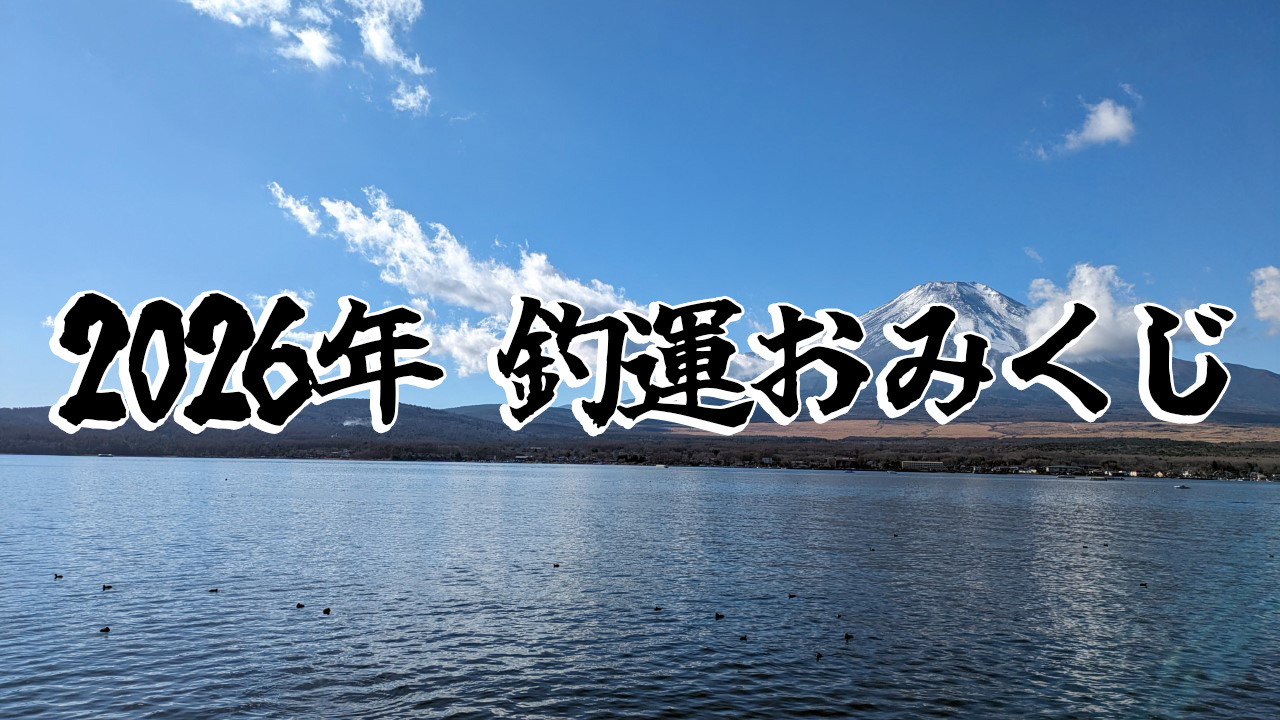
.jpg)


.jpg)
-Dec-26-2025-01-00-45-5413-AM.jpg)


