エリアトラウトで磨かれた緻密な操作と再現性の思考を武器に遠藤肇さんはアユルアー(アユイング)の可能性を追求している。わずかな差を釣果に変える、その技術と思考法に迫る。
エリアトラウトで磨かれた緻密な操作と再現性の思考を武器に遠藤肇さんはアユルアー(アユイング)の可能性を追求している。わずかな差を釣果に変える、その技術と思考法に迫る。
写真と文◎編集部
遠藤肇(えんどう・はじめ)プロフィール:深谷市在住。第12回トラウトキング選手権でトップマイスター(総合優勝)の称号を手にしたJACKALL TIMONフィールドスタッフ。大芦川F&Cフィールドビレッジをホームに活躍。エギング、ヤエン、ショアジギング、カヤックなど釣りなら何でも好きなマルチアングラーでもある。3年ほど前からアユルアーの沼にハマり、アユシーズンは毎週末釣行するほど
アユルアーとエリアトラウトの共通点
アユルアーを新しく始める人には他のさまざまなルアー釣り経験者が多い。今回釣行に同行させてもらった遠藤肇さんはエリアトラウトの手練れ。トーナメントも盛んで選手としてしのぎを削っているアングラーが多い世界だ。
ルアーを泳がすレンジをセンチメートル単位で微調整したり、同じレンジを泳がせるにしてもロッドの角度によるスイム姿勢の変化=泳ぎの質の変化で魚の反応にアジャストしたりといった、繊細さが重要視される。実際、そういった微調整で魚の反応が変わり釣果に差がつくから、トーナメントの勝敗がそこで決まる場面も多々あるのだ。
第12回トラウトキング選手権でトップマイスター(総合優勝)に輝いた遠藤さんは、「アユでもその日、そのタイミングによって、エリアトラウトと同じくらいわずかな差で釣果に差がつくことがあります」と断言する。
「たとえば、石の横へルアーを通そうとしたときに、リールを巻いて泳がせるのと、ロッドでさびいて通すのとで反応が変わったことがありました。同じスピードで引こうと思っても、ロッドで引くほうがわずかに遅くなりがちですよね。その差で釣果に差がつくことがあるんです」
そんな遠藤さんはアユルアーについては友釣りの動画を見てイメージをふくらませることも多いという。
「アユルアーでは下流から引いて釣るのが基本とされていますが、それだけでは追わせられないアユも多くいると感じています。生きたオトリを使った泳がせ釣りではオトリはいろいろな方向に泳いでいますよね。流れに対して直角に石を横切らせたときに掛かる場面もあれば、オトリが下流へ反転したときに掛かっているシーンも見たことがあります。そういった生きたオトリのいろいろな動きをルアーで表現できないかと思っているんです」

再現性を重視する方法論
相模川ではダウンクロスにキャストしてルアーをドリフトさせながら下流から巻き上げてくる操作法が基本となる。こぶし大の石の中にそれよりやや大きな石が点在するシチュエーションが多いからで、アユがつく目印となる大きな石が少ない。そのため高範囲へ広くルアーを通して追い気のあるアユを効率よく探ることが釣果につながりやすいからだ。
「その操作でも数投おきに巻きスピード、ロッドの角度、キャストの距離を変えて探るようにしています。同じ立ち位置から同じ方向へルアーを投げているのですが、ルアーが通るコースと速さを微調整しています。1投ごとに変えないのは再現性を確認するためです。そうやって見切られるのを防ぎながら、その日のパターンを探っています。先週も相模川に釣行していますが、周囲に何人か並んで釣りをしているなかで、私にだけ連発する時合が来ました。そのときやっていたのは、流れに乗せながら速めに巻いて時おりグリグリグリッとさらに速くリールを巻いて加速させる方法です。一投のなかで繰り返すのですが、最初のグリグリでヒットしていたので流れに対して直角に近い角度で速く横切らせる動きが効いたんです。
完全に下流から通してくるダウンの釣りは誘いのバリエーションを作りづらい。追い気が強いときならいいですが、それでダメならあきらめるしかない。でも、ほかのルアーフィッシングと同じように、アユもリアクション(=反射)で反応させる余地があると思っています。まだまだ確立されていない釣り方がいろいろありそうで、それを探しながら釣りをするのが楽しいですね」
やみくもに探るのではなく、1投ごとのねらいを整理しながら試行を重ねていく。それこそがエリアトラウトで培われた方法論だ。アユがヒットしたり、ハリに触れたりといった反応が得られれば、それを再現することでその日のパターンを見つけることが可能。ただし、自分が行なっている操作で、ルアーがどのコースをどう泳いでいるかを把握し、それを精度よく再現できることが重要だ。

タックルは感度重視
そのため遠藤さんはタックルに感度を求める。ロッドはチューブラーモデルのナワバリレンジNR-C86/100Mを愛用。メインラインはPEが絶対だという。
「最近は弱いアタックも乗せやすくバラシを減らせるしなやかなソリッドティップモデルが人気ですが、やはり感度の面ではチューブラーが有利です。その感度で何を見ているかと言えば、川底の石の入り方です。私自身エリアトラウトではクランクベイトのボトムノックを得意にしていることもあって、川でもルアーが底を叩く感触から小石の中に大きな石がどれくらいの密度で入っているか、その位置はどのあたりか、といった情報を大事にしています。それがあって初めて精度の高いアプローチができます。あとはハリに掛からなくても、アユがハリに触れた感触が分かることも必要ですよね。反応があった場所やルアーの挙動、その日の活性を判断して次の展開を考えますから」
なおチューブラーのロッドでもやり取りの際にロッド捌きを適切に行なえばバラシは減らせる。遠藤さんはロッドティップを下げたポジションでゆっくりリールを巻いてやり取りしていた。

ロッド:ナワバリレンジNR- C86/100M(ジャッカル)
リール:タトゥーラSV TW 100H(ダイワ)
ライン:PE0.6号
リーダー:フロロカーボン1.5号
ゼロか1かはわずかな差で
当日の模様に入ろう。相模川で待ち合わせたのは午前9時。遠藤さんはエリアトラウトで知り合った仲間たちと一緒に、和気あいあいと川に立ち込んでいた。人気ポイントのため遠藤さん一行と合わせて10人ほどが瀬の上流から下流にかけて並んでいる。が、どうやら難しい日に当たってしまったようす。全員を見渡しても、10人合わせて時速3尾程度のサオの曲がり具合だ。遠藤さんもすでに1尾をキャッチしているというが「釣れるとしたら水温が上がる10時以降でしょう」と朝の低調を分析。
遠藤さんのルアーローテ術
この間に実践しているルアーローテを聞いてみる。
「最初に投げるのはオトリミノースリムでサーチすることから始めます。ウエイトをなるべく下側に配置した設計で、ロールがメインの大人しい安定したアクションのミノーです。最近はほぼこれで通してしまうことも多いです。これで反応が無ければ、ジョイントのテールを横に振るアクションが特徴のオトリミノーを使います。こちらはアクションが一段強い位置づけで、動きの質の差で反応を探ります。それでもダメなら、オトリミノーバイブです。バイブレーションはフローティングミノーでは入れられない流れをねらうのに使われることが多いですが、私は石にコンタクトさせたときにアクションが破綻しやすいのがメリットだと感じていて、その破綻する動きで追い気の乏しいアユをリアクション的にアタックさせるのをねらった選択です」
その言葉どおり、オトリミノーバイブを投げていたときにヒットした。このアユは残念ながらネットに入らなかったものの「着水してフォール中にゴンッと持っていかれました」と遠藤さん。
「オトリミノーバイブはフォール中に横方向へスライドするんですよ。いままでも同じようにヒットしたことが何度もあって、これも予想外の動きに対するリアクションだと捉えています」
次に遠藤さんはメインの瀬の上流側で、側流に分岐する幅の狭いチャラ瀬をねらい始めた。アユが目視できる流れの中へ、オトリミノースリムを執拗に通してみるが全く追うそぶりを見せない。そこで、ジョイントタイプのオトリミノーに代えてみると1投目でヒットした。

「アクションの差ではっきり差が出ましたね。釣れてよかったけど、すっごいセレクティブ」ここで連続ヒットと行かないのがこの日の難しさ。川を観察すると、立ち込んでいる足もとを15~20cmクラスのアユが上流へ向かって泳いでいくのが見えた。
「アユが定位せずに移動している日は追いが悪いですよね。3日前に来た時もその兆候があって、マズいなと思ってたんですよ」

釣り方を変えて会心の一尾
このままでは終われないと一層気持ちを込めてキャストを続けていると、午後2時を回ろうというタイミングで周囲の人にアユが掛かり始めた。アユが掛かる釣り方にパターンを見いだせるなら、これまで掛からなかった釣り方にも法則があるということ。
遠藤さんはこの日メインで試していたクロスの釣りを捨て、ダウンから引いてくる釣りにシフト。これが奏功し、アユが触った感触を得た。次のキャストではそのスポットにルアーが差し掛かったところで巻くのを止め、手もとで8の字を描くようにロッドティップを左右に振ってアユを挑発。ティップの動きをワンテンポ遅れて追いかけるオトリミノースリムの動きに、たまらず体当たりをした野アユの背中を、チラシバリががっちり捕らえたのだった。


\あわせて読みたい/ アユルアー(アユイング)完全ガイド【仕掛け・ルアー・釣り方・装備まで解説】

\あわせて読みたい/ アユルアー(アユイング)を1年やって気づいた4つの大事なポイント
※このページは『つり人 2025年9月号』を再編集したものです。



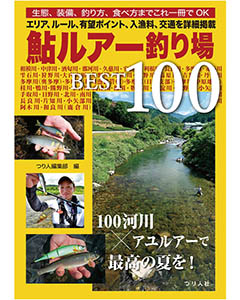






.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)





%20(2).jpg)
-Feb-16-2026-07-21-01-9585-AM.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)


