長良川河口堰運用から30年目の節目となる2025年7月6日、岐阜市内において市民グループがシンポジウムを開催した。この30年間、なにも進展がなかった現実に対し、対立ではなく対話が必要との発言もあったが、河川行政が対話拒否の姿勢のまま。一方で、隣国・韓国では科学的なデータを元にして河口堰の常時開放を実現していた。長良川が奪われたもの、そして取り戻すべき未来について、シンポジウム後半の議論をレポートする。
写真と文◎浦 壮一郎
河口堰が長良川にもたらした悪影響
長良川河口堰のゲートが閉じられてから今年で30年が経過した。1995年7月6日、長良川河口堰は運用を開始し、河口域に広がっていた汽水域は消滅。さまざまな生き物たちが激減したまま現在にいたる。
30年目の節目となる2025年7月6日、流域市民からなる『よみがえれ長良川実行委員会』の主催によりシンポジウム「長良川河口堰運用30年」が岐阜市内で開催され、およそ200名の市民が参加。依然として人々の関心が高いことをうかがわせた。
河口堰運用の是非および運用後の環境悪化についてはシンポジウム冒頭、主催団体である『よみがえれ長良川実行委員会』共同代表の粕谷志郎さん(岐阜大学名誉教授)による解説が簡潔明瞭だった。要約すると以下のようになる。
河口堰の当初目的は伊勢湾岸のコンビナートに工業用水を供給することであったのだが、この30年間、工業用水は一滴も使用されていない。水道用水を含めても河口堰の開発水量に対し使用されているのはわずか16%程度しかないという。
治水についてはどうか。もともと河口にある堰に治水効果など期待すべきものではない。が、河床の浚渫(掘削)によって洪水を安全に流すとしながら、浚渫すると塩水の遡上が顕著となるため河口堰でそれを阻止するという間接的な治水の論理が用いられてきた。つまり河口堰は塩害を防止するための施設だといえる。粕谷さんは次のように説明した。
「長良川河口部は伊勢湾台風の一時期を除いてほとんど塩害を経験しておりません。過去(運用前)の長良川での塩分濃度の上昇を見ますと1万mg/L、これが河口から約5〜10kmくらいの川底を上る程度です。機構が主張する1万8000mg/Lなんてどこにも見あたらない。これは過大なシミュレーションというよりもほとんどフェイクに近い」
つまり長良川河口堰は利水(工業用水&水道用水)にも、治水にも、塩害防止にも不要な施設だったことになる。その一方で環境悪化は深刻なものとなった。
「ヤマトシジミはあっという間に死滅しました。潮の干満がなくなるためアシ原はほとんど枯れてしまいました。ゴカイの仲間など汽水性の生き物も完全に死滅しております。アユなどの回遊魚、これにも大きな障壁になっている。生まれたてのアユの仔魚は広大な真水の湖を下れません。5日もすると死滅してしまう。対して漁協の人たちは受精卵を作って河口堰の下までトラックで運んでいます」
いったい長良川河口堰とは何だったのか。この30年間は何だったのか。河口堰のゲートは国土交通省のメンツ維持のためだけに閉じられている、そう感じている流域住民は少なくないはずである。

画期的だった淀川流域委員会
パネリストのひとり、宮本博司さんは河口堰建設中の当時、国土交通省から水資源機構へと出向し河口堰建設所長として赴任した現場の責任者だった。(※長良川河口堰建設所は運用後の現在、長良川河口堰管理所と名称が変更されている。)その後は本省河川局を経て近畿地方整備局へと異動となり『淀川水系流域委員会』の設立に尽力。2006年に国交省を退職している。
長良川でさまざまな反対運動と対峙したその反省から、淀川流域委員会では次のように画期的な手法を取り入れている。そのいくつかを列挙すると、まずは委員を国交省が選ばないこと。国や都道府県が委員を選ぶことはすなわち御用学者と同義だからである。そこで第三者に委員の選択を依頼したという。
次に事務局は事業主体である国交省ではなく民間のシンクタンクに依頼するとともに情報公開の徹底を図った。 さらに原案は国交省が作成するのではなく、原案がないままゼロからのスタートとし、どのような河川にするのかを役人、学者、住民のそれぞれが議論しながら理想像を模索したというのである。
ダム事業に固執する国交省
ところがその後、画期的といわれた淀川流域委員会は形骸化してしまう。淀川のようなことを全国で始めたらダムが建設できなくなる、そんな危機感が省内に広がったのだろう。淀川潰しが始まったのだという。
従来治水へと逆戻りしてしまった淀川流域委員会および国交省だが、時を同じくして旧来型治水計画の誤りが次第に証明されてゆく。全国各地で堤防の破堤が多発したのである。結局、ダムや河道整備で洪水を制御することはできなかったのだ。
その影響もあり、国土交通省は令和4年5月27日に『河川整備基本方針の変更の考え方について』と題するひとつの指針を発表する。この時から『気候変動を踏まえた計画の見直し』と『流域治水への転換』といった考え方が示されることになった。ところが指針にはダムや河川改修等の対策の加速化が記されており、結局は旧来型治水計画とそう大きくは変わっていないという。
「国交省の言う流域治水は結局、これまでのダム建設・河川工事最優先という点で全く変わっていない。基本高水まではダムで貯留、河道で流下させ、(それを超える)想定外の洪水に対しては流域治水をやりましょうというものなので、これでは『まやかしの流域治水』だと思います」(宮本博司さん)
元国交省職員で治水計画に携わってきた宮本さんの言葉は重い。流域治水をうたいながらダム事業に固執し、かつ住民との対話から遠ざかってしまった国交省。長良川河口堰においてもその姿勢は同様である
我が国の先を行く韓国の河川行政
対して、おとなり韓国では河口堰の常時開門を実現している。『よみがえれ長良川実行委員会』では昨年9月、韓国はナクトンガン河口堰の視察を行なったという。その事例について武藤仁さん(よみがえれ長良川実行委員会・事務局長)が報告した。
ナクトンガン河口堰は韓国の南、釜山近郊に位置する。長良川河口堰の総延長は661m、ナクトンガン河口堰は510mと規模は若干小さいが、これはナクトンガンの河口に中州があるためだという。
国土交通省から環境省の管轄に変更
完成は1987年、同年に運用を開始したが、長良川同様、汽水域の生物多様性は失われることとなった。が、2019年より開門調査を実施し、2022年より常時開門に踏み切っている。それまでの過程について武藤仁さんは次のように説明する。
「一番凄いのは、今まで韓国でいう国土交通省が河口堰を管理していましたが、それを環境省に変えたことです。これ以降、根本的に変わりました」
河口堰を建設した国土交通省がそのまま管理運用していた場合、環境への悪影響が顕著であったとしても、彼らはその正当性を主張するだけだろう。ところが韓国では管理運用を環境省に変更した。そうすることで冷静な判断が下されるようになったというわけである。
「日本と異なるのは、水門開放実証実験においてもきちんとしたシミュレーションがあったことです。堰のゲートをこれだけ開けたらこれだけ塩水が遡上するということが計算されていました。水門開放実証実験は実質、シミュレーションどおりになるのかどうか、その確認でもありました。結果がほとんどシミュレーションどおりだったことで、2020年から常時開門に運用を移行したわけです」
塩害対策はリアルタイムにモニタリングしてデータを公表
では塩水が遡上した場合、塩害による農業への影響はどうなのか。この点についてもモニタリング結果を公表することで農民の不安も解消されているようである。
「塩分予測モデリングおよびモニタリングによって、今どこまで塩分が上がっているのか分かるようにしていました。塩害が絶対に発生しないように運用しているわけです。農民も塩分が上がってきたら困るということで開門に反対してきたので、その心配を軽減するために52ヵ所の塩分濃度計を設置し、リアルタイムに知らせています」
長良川河口堰はゲートを開放すれば塩害が発生するとして危機感をあおるのみだが、韓国はすべてを包み隠さず公表することで信頼を得ているというわけである。
韓国におけるデータの公開については、パネリストの三石朱美さん(元生物多様性の10年(UNDB)市民ネットワーク)も同様の解説を行なった。同氏も『よみがえれ長良川実行委員会』メンバーらとともに韓国を視察している。
「日本では環境アセスメント等の情報公開においても、せいぜい年に何回か定期的に検査したものがPDFになっているだけで、今この瞬間どのようなことが起こっているかという情報はどこにもありません。ところが韓国では我々外国人でもデータを見せていただける。一番びっくりしたのは、そのデータをホームページでリアルタイムに公開していたことです。学ぶべきことは学ぶべきと思いました」
どうやら日本は一歩も二歩も後れを取っているようである。運用に自信を持っているからこそ情報公開できる韓国に対し、自信のない我が国の行政は言い訳を繰り返しながら情報をひた隠しにする。しかも運用から30年という節目にあってシンポジウム会場に足を運ぼうともしない、それが現実である。
河川行政はなぜ議論の場に来ないのか
まやかしの流域治水と酷評された河川整備基本方針であるが、そのあり方を議論する河川整備基本方針検討小委員会の委員を務めてきたのが岐阜協立大学・地域創生研究所所長の森誠一さんである。自身が関わってきた関係から一定の評価をしつつも、次のように釘を刺した。
「いかさまとまでは言いませんが、このポンチ絵をどこまで実装できるかということについては、現状かなり異議を持っています」
こう話した上で、他の登壇者と同様、国交省および水資源機構から誰一人としてシンポジウムに参加していないことを問題視した。
「運用から30年という今は非常にタイムリーで、その歴史や評価の点でさまざまな問題を投げかけてくると思う。その場に事業者が来ていない。事業者が来てしっかりと議論することがきわめて重要だと思います」

結論ありきの公共事業
事業者が議論の場に出て来ない理由については次のような意見もあった。
「水資源機構や国交省がここに来られない理由は、怖いからだと思います」
こう話すのはパネリストのひとり、東京大学大学院教授の蔵治光一郎さんだ。同氏は愛知県長良川河口堰最適運用検討委員会の委員を務める形で長良川の問題に関わってきた。
「相手が怖がって来られない状況に対し、怖くないんだよというメッセージを送らないと次のステップに進めないのかなと、率直に感じているところです」
特に長良川河口堰に対する反対運動は、1997年の河川法改正に繋がったといわれるほど国交省に影響を与えるものだった。その怖さゆえに流域住民との話し合いを避けてしまうということだろうか。

対して、前出・宮本博司さんは次のように話した。
「絶対に開門しないとの結論が決まっていれば、何を言われてもNOと言うしかない。だから来にくいんです。対立から対話(を目指す上で)、対話に必要なことは結論を持たないことなんです。みんなと議論した上で、自分たちがいいと思った意見は変えてもいい、変えないといけないんだと(考えるべき)。絶対にこのダムは造ると決めてかかるから、いろんなこと(反対意見)を言われると逃げたりごまかしたり、嘘ついたりするわけです。この計画は止めてもいいんだといった柔軟性があれば、住民と行政との間に信頼関係ができて、良い結果が出てくるんだと思います」
仮にゲートを常時開門したらどうなるか。本流に大きなダムのない長良川の場合、河口堰によって失われてきた生物多様性は開門からさほどの期間を要することなく回復軌道に乗ることが予想される。河口堰の影響を軽微としてきた国交省の主張は脆くも崩れ去る可能性が高く、議論の場を避けているのはそうした理由からだと想像できるのである。

ネイチャーポジティブの目標は実現不可能?
他方、生物多様性条約の締約国会議では、2020年までに生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施するとしている(すでに+5年が経過しているのだが……)。さらに2030年からは生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急行動をとること、そして2050年には自然と共生する世界を実現することが採択されている。
これら国際会議に詳しい前出・三石朱美さんは次のように説明した。
「COP10の愛知目標は長期目標として2050年までに自然と共生する世界を作り、そのための短期目標として2020年までに生物多様性の損失を止めるための効果的かつ緊急な行動を実施するとしています。ところが実際に損失が止まったとは到底思えないわけです」

生物多様性の損失を止めるとした2020年(COP10)の目標は我が国、愛知県名古屋市で開催し採択された短期目標である。それすらも守れず、むしろ損失を加速させているのが先進国を標榜する我が国の現状だということになる。
さらに、この愛知目標を発展させ採択されたのが、昆明・モントリオール生物多様性条約の締約国会議(COP15)の2030年目標(自然の損失を食い止め回復軌道に乗せる/ネイチャーポジティブとも呼ばれる)であるわけだが、もはや我が国では実現不可能だろう。いまだ損失を加速させているのが日本の行政であるだけに、このままでは世界に約束したことを守れない国、それが日本だということになってしまいそうだ。

食糧安全保障の視点で見る河川の再生
余談になるが、これまで30数年ものあいだダム等河川関連の公共事業を取材してきた筆者だが、思えば取材を始めた当初、さまざまな人々から豊かだったかつての川、その姿について話を聞いた。その方々は仮に今現在もご存命であれは110歳あるいはそれ以上の古老たちである。彼らは戦中あるいは戦後すぐの時代を知り、当時の川の姿を語ってくれたのだ。
敗戦濃厚あるいは敗戦直後の日本はいうまでもなく食糧難に喘いでいたとされる。しかしその多くは都市部であり、古老たちによると自然豊かな田舎町は「言うほど困っていなかった」らしい。その理由は明快である。 川に行けばたくさんの生き物がいたからだ。春にはマス(サクラマスやサツキマス)たちが上流を目指し、夏には川の色が変わるほどのアユ、関東以北なら秋にはサケが遡上してきた。ある地域では家にいながらにしてアユの遡上が分かったという。アユの香りが川の周辺全体に漂うほどの遡上量だったからである。
その他の魚類、ウグイやオイカワ、ゴリ、ドジョウ、ウナギなども簡単に捕獲できるほど豊富で、このほかカニやエビなどの甲殻類も水際で普通に見られたという。戦時下でも彼らはそれらを捕獲することで生きてゆくことができたのである。
干潟も同様である。東京湾の取材時に聞いた話でも、やはり「困らなかった」と古老たちは話していた。埋め立てられて消失した干潟にはアサリなどの二枚貝やシャコやカニなどの甲殻類など、豊かな自然が見渡す限り広がっていたからだ。
豊かな自然を取り戻すことは、食料自給率の向上にも繋がる
つまり当時、国は破れても山河はあったということ。今はどうだろうか。食料自給率がきわめて低いとされるなか食糧安全保障の議論として話題に上るのはコメ問題ばかり。確かに日本人の主食はコメなのだが、それだけではない。高度成長期からバブル期、そして現在にいたるまで、農業を優先するあまり漁業が犠牲になってきたその帰結が今の姿であり、川に棲む淡水魚や甲殻類は全国的に激減の一途をたどっている。
他方、国際情勢の変化により輸送航路が閉鎖されると輸入食材の供給が不安定になると示唆されている。日本国内が戦時下にならずとも、再び食糧難に陥る可能性はゼロではないということだ。国破れて山河もない、それが我が国の現実なのである。 政府は国土強靱化といいながら、まだまだ山河を破壊することに躍起になっている。これでは強靱化どころか弱体化であり、食糧安全保障の点でも懸念材料が増してゆくばかりである。
長良川を取り戻すために……
長良川に話を戻すが、解決策はハッキリしている。長良川の生物多様性を回復させるには河口堰のゲート開放が必須条件であり、それはネイチャーポジティブの目標および食糧安全保障の問題とも無関係ではない。
しかし運用から30年もの間なにひとつ進展がなく、また担当行政が住民との対話を拒み続けてきたことからも、彼らにとっての関心事は国の行く末ではなく自身らのメンツ、利権の維持にあると考えるほかない状況である。
シンポジウムでは対立から対話を促す議論もなされたが、担当行政が議論の場に出て来ないのであれば先に進むのは難しいだろう。シンポジウムの終わりに前出・宮本博司さんは次のように締めくくった。
「地域のための公共事業であり、その原資は税金ですから住民と行政が対立すること自体おかしいんです。運用から30年が経過したこの長良川から、全国に発展するような住民と行政との関係を作っていきたい。それが私が考える今後の展望であります」
長良川河口堰の開門に関する議論は、岐阜県において『長良川河口堰調査検討会』、愛知県においては『長良川河口堰最適運用検討委員会』、国土交通省中部地方整備局においては河口堰も対象に含まれる『中部地方ダム等管理フォローアップ委員会』および『長良川河口堰の更なる弾力的な運用に関するモニタリング部会』が設置され、それぞれに議論を重ねてきた。
しかしバラバラに実施しているという印象は否めず、3者合同の円卓会議の必要性が指摘されている。その実現が長良川再生における本当の意味での第一歩だといえるのかもしれない。
※このページは『つり人 2025年12月号』の記事を再編集したものです。




.jpg)
.jpg)
%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg)

-1.jpg)

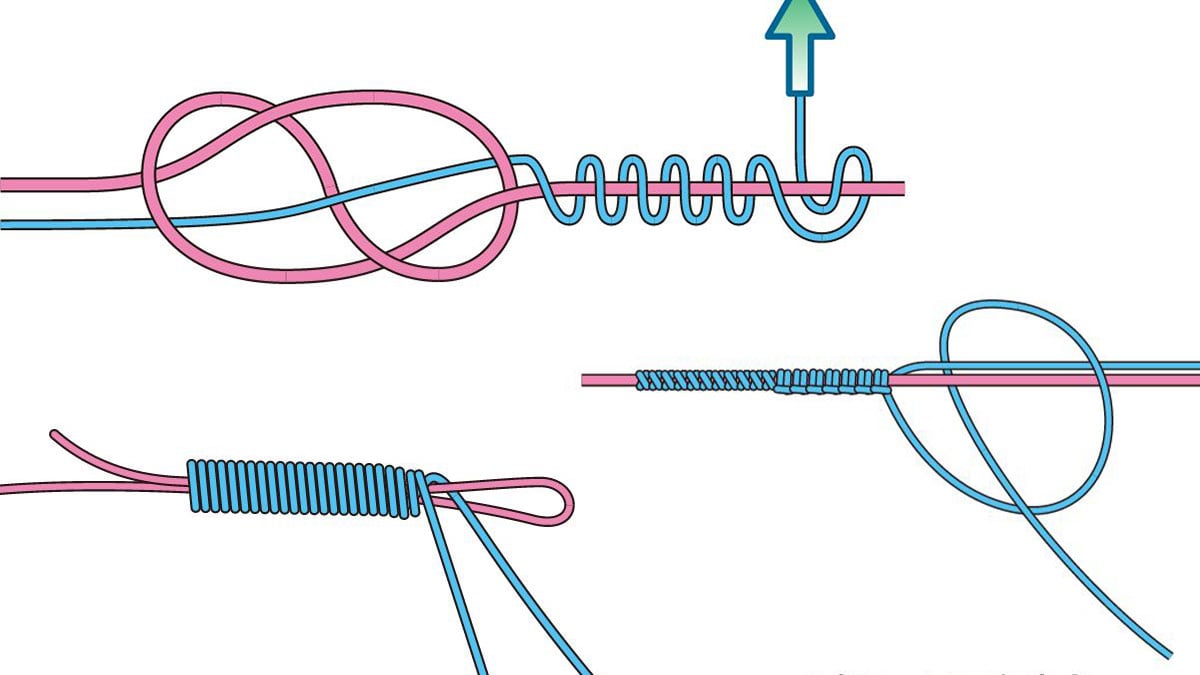

.jpg)

.jpg)





.jpg)
-Mar-10-2026-02-12-50-0678-AM.jpg)





.jpg)
.jpg)

