長良川河口堰運用から30年目の節目となる2025年7月6日、岐阜市内において市民グループがシンポジウムを開催した。対立から対話を促す議論もなされたが、会場には河口堰を管理する水資源機構そして国土交通省の関係者の姿はなく、対話拒否の姿勢が鮮明となる形となった。長良川河口堰は何をもたらしたのか、そして奪ったものとは何か。
写真と文◎浦 壮一郎
河口堰運用から30年で何が変わったか
2025年7月6日は長良川河口堰の運用から30年目の節目だった。1995年の同日、岐阜県の長良川では河口堰のゲートが閉じられ堰上流の汽水域は消滅。長良川を取り巻くさまざまな繁華が、この日を境に失われていったと感じているのはおそらく筆者だけではないだろう。
筆者が初めて長良川の畔に立ったのは河口堰運用前の、まだ建設中の時代だった。長良川河口には広大な汽水域が存在し、多くの魚類たちが回遊を繰り返していた。春にはサツキマス、夏にはアユ、そのほかヨシノボリなどゴリの仲間、カジカやアユカケ、そしてカニやエビなどの甲殻類など、さまざまな生き物たちの存在が人々を魅了してきたといえる。
そして、長良川流域の文化はまさに、それら天然資源の存在によって繁栄してきたといっていい。河口の長島、桑名から川沿いに遡ると、岐阜、関、美濃、そして郡上八幡と、川文化がもたらした人々の豊かな生活を実感することができた。それは長良川を眺めながら車を走らせているだけでも充分だった。瀬のなかには天然アユをねらう釣り人が所狭しと並び、橋の上には川を覗きながら雑談にふける人々、ウェットスーツのまま道路を横断する川漁師、そして淵で泳ぎ、飛び込む川ガキの姿など、人々の暮らしはまさに長良川と共にあると感じたものだ。
そして現在、永遠に続くはずだった活況を手放した長良川はもの寂しさすら感じることがある。川の生き物が減ったことで、人々の関心も長良川から遠ざかってしまったのかもしれない。物理的には近くを流れる川でも、関心を失ってしまえば遠くの川と変わらないということだろうか。
河口堰運用から30年となる今年7月6日、流域市民からなる『よみがえれ長良川実行委員会』の主催によりシンポジウム「長良川河口堰運用30年」が岐阜市内で開催された。主催者によると国土交通省や水資源機構に対して同シンポジウムへの参加を要請していたというが、残念ながら会場に河口堰を管理運用する当事者の姿は見られなかった。

長良川河口堰建設の歴史
長良川河口堰の計画が世に初めて知らされたのは1959年。当時の朝日新聞に長良川河口ダムの記事が掲載されたことによる(当時の報道では「ダム」となっていたものの、日本では15m以下のダムを堰と呼ぶことから、その後は河口堰が定着)。 もともとの建設目的は、高度経済成長期のさなかとあって伊勢湾岸のコンビナートに工業用水を供給することであったが、水需要が不要だと分かると目的を変えながら計画は継続された。一応は治水も目的に掲げられているが他のダムのように洪水を貯留するというものではない。その論理は以下のようになる。
洪水を安全に流すためには浚渫(河床掘削)が必要になるが、浚渫すると塩水がソ上して農地に塩害を引き起こす可能性が生じる。そこで河口堰により塩水を食い止めるという理屈である。つまり治水目的の施設というよりは塩害防止が主たる目的であると同時に、河口堰は農業を優先し漁業を切り捨てる施設だといい換えることもできるだろう(塩害についてはシンポジウムでも指摘あり/後述)。
さまざまな反対運動が展開
もともと水が不要となった時点で中止がふさわしい事業だっただけに、さまざまな反対運動が展開されてきた。古くは1960年代、旧海津町と旧平田町の漁民を中心として長良川河口ダム反対期成同盟が発足。また1967年には両町議会で河口堰反対決議をあげたものの、水害対策等に同意する形で1978年には推進に転じた。
河口堰建設に反対していた漁協はどうか。1988年、最後まで反対していた赤須賀漁協を含む3漁協が着工に同意。ついに同年、河口堰建設は着工され、1995年に運用を開始したというわけである。
ところが反対運動は1990年代に入ってからも続いた。地元の流域自治体や権利団体の運動は終息に向かったが、本体着工による危機感から、その運動は全国区へと発展していったといえる。特に全国各地の一般市民や自然愛好家、釣り人やカヌーイストらが現地に集結。シンポジウムのほか周辺各地でのデモ、水上からのカヌーデモなど、運動は活発化した。この長良川河口堰反対運動は全国の公共事業問題の象徴的存在であるとともに、1997年の河川法改正の際、環境の保全と住民参加を盛り込む契機となったといわれている。
しかしながら1995年7月6日に河口堰のゲートが閉じられた長良川は、予想されたとおり衰退の一途を辿り現在に至る。30年が経過した今も状況は悪化したまま。その節目にあって、30年を振り返るとともに改善策を見出すためのシンポジウムだったといえるだろう。

不要だった長良川河口堰とその影響
シンポジウムの冒頭、主催団体である『よみがえれ長良川実行委員会』共同代表の粕谷志郎さん(岐阜大学名誉教授)は、運用後の現状を次のように説明した。まずは当初の目的とされた利水(工業用水の確保)についてである。
「この30年間、工業用水は一滴も売れておりません。知多半島などへ水道用水が使われておりますが、確保した水量のせいぜい16%。民間会社ですと破産間違いなしといえます」
河口堰運用前、知多半島は木曽川水系の暫定水利権によって水道用水が確保されていたが、暫定であるという理由で河口堰の水に置き換えられた。つまり木曽川からの供給で何ら問題なかったが、河口堰運用を正当化させるため押しつけられた形である。

「治水」についても役割は限定的
では治水についてはどうか。粕谷志郎さんは続ける。
「2004年の23号台風の時、毎秒8000立方mの水が流れました。長良川は毎秒7500立方mで安全が確保できるように管理されているわけですが、知らぬ間に8000立方mが流れていた。(河口堰の治水は)浚渫をして洪水を安全に流す、そのために塩水がソ上するのでこれを阻止しようという理論ですが、ようするに河口堰のある河口部に関しては(河口堰とは関係なく)治水上も安全な状態だということになる。利水においても治水においても、ほとんど役割は果たしていない施設だといえると思います」
塩害の防止についても疑問符
塩水がソ上すると農地に塩害が生じるとの理由で、それを防止するのが河口堰だったが、肝心の塩害はどうなのか。
「長良川河口部は伊勢湾台風の一時期を除いてほとんど塩害を経験しておりません。(水資源機構の主張は)あくまで計算上の塩害です。(計算上の)塩分濃度は1万8000mg/L。ただしこのようなことは起こっておりません。過去(運用前)の長良川での塩分濃度の上昇を見ますと1万mg/L、これが河口から約5〜10kmくらいの川底を上る程度です。1万8000mg/Lなんてどこにも見あたらない。これは過大なシミュレーションというよりもほとんどフェイクに近い」
生態系には明確なダメージを与えた
この30年で不要だったことを証明してしまった河口堰だが、ゲート閉鎖の影響は予想通り深刻なものとなった。
「ヤマトシジミはあっという間に死滅しました。潮の干満がなくなりますのでアシ原はほとんど枯れてしまいました。現在までに約90%が消失しております。それから潮が引きますと砂浜に無数の小さな穴が見えましたが、そこにはゴカイの仲間がいた。これら汽水性の生き物も完全に死滅しております。それから長良川を代表するアユなどの回遊魚、これにも大きな障壁になっている。生まれたてのアユの子どもは広大な真水の湖を下れません。5日もすると死滅してしまう。対して漁協の人たちは受精卵を作って河口堰の下へトラックで運んでいる。トラック輸送によってなんとかアユが生活史を維持している状態です」
これら粕谷志郎さんが説明した現状は、河口堰のゲートを開放することで改善に向かうことは間違いない。しかし国土交通省および水資源機構はいまだ頑なな姿勢を堅持したままである。

釣り人らも河口堰反対運動に集結
『長良川河口堰の歴史を振り返る』と題して講演した富樫幸一・岐阜大学名誉教授は、先に述べたような河口堰の歴史を解説。特に1990年代の反対運動については以下のように話した。
「毎年、伊勢大橋付近ではカヌーイストによるデモが行なわれたほか、釣り人たちがものすごい運動をしてくれた。そういう意味では反対運動もいろいろな段階があって、この頃になると全国的な盛り上がりになっていったのが長良川の特徴だと言えます」
当時はアウトドアブームとあって20〜30代の自然愛好家らが多かったと記憶している。つまり川への関心が高かった時代でもあっただけに、全国のアウトドア好きな若者たちが長良川に集結したのだ。そして釣り人たちも、当時は自然保護運動に貢献していたのである。

各政党も事業を見直すべきという方針だったが……
「しかもその動きは国レベルを動かしました。それまではだいたい国が何かを決めて地方に下ろす、旧河川法もそうですが、国の方針でローカルな開発をやっていくという形でした。ところが、この時の運動は党派を問わず、自民党から共産党まで『公共事業を見直すべき』という方針でした」
ところが長良川河口堰の建設は止まらず、運用から30年が経過した今もゲートは閉じられたままである。富樫幸一さんは河口堰の歴史を振り返った上で次のように締めくくった。
「これから100年、人口はこのままいくと半分になる。水道事業も水道の収入も維持できなくなります。水道料金の値上げや(水道管の陥没)事故もあちこちで発生していますし、それらに対応する人手も不足しています。一方で各ダム、導水路の事業費が2倍以上に膨れあがっている。これまでのやり方を根本的に見直し、環境を守り、持続可能な河川、地域というもの維持していかなければなりません」
ゲート開放の議論は主に愛知県で『長良川河口堰最適運用検討委員会』が議論を進めているが、岐阜県はゲート開放に否定的だという。

元長良川河口堰建設事務所長の奮闘
当時、国土交通省から水資源機構へと出向し、同機構の河口堰建設所長として現場の責任者だった宮本博司さんも登壇し、注目を集めた。2006年に国交省を辞職して以降、市民グループ主催のシンポジウム等に呼ばれることの多い宮本博司さんは冒頭、国交省と河口堰を管理する水資源機構へ注文を付けた。
「河口堰運用30年という節目ですから、本来は国土交通省あるいは水資源機構の職員がこの場に来て、皆さんと一緒に30年間を振り返るべきだったと思います」
この意見は登壇したパネリストの大半が同意するものであり、また会場に訪れたおよそ200名の参加者も同意見だったに違いない。
長良川河口堰の反対運動が河川法改正につながったと述べたが、その際もさまざまな抵抗があったようである。
「それまでは川やダムの計画は国交省が策定し、それを住民に知らしめるものでした。それではいけないと考え、新河川法では計画を策定する際に住民の意見を反映させるとしたわけです。今となってはこれでも足りなかったと思ってますが、当時はいろいろ抵抗がありました。例えば省内の他部局です。国交省には河川局のほかに道路局だとか都市局だとか、いろいろあったわけですが、住民の意見を聞くなんてことを河川局が制度として法改正したら、自分たちまでやらないといけないじゃないかと。もっとひどい抵抗は河川局OBです。なぜ住民の意見を聞いて判断を変えたりするんだと言われました」

対話を拒否する行政。ゲートが開く日は来るのか
宮本博司さんは水資源機構の河口堰建設所長の後、本省河川局を経て近畿地方整備局へと異動となった。そこで取り組んだのが淀川水系流域委員会の設立である。その画期的な手法は当時『淀川方式』と呼ばれ注目を集めた。
「まず委員を国交省は選ばない。実はこれ、初めてのことだったんです。今でも国とか県がつくる委員会は国と県が委員を選んでいます。だから自分たちの都合のよい委員を入れている。いわゆる御用学者です。それをやっていると初めからお墨付き委員会を作るようなものですから、淀川では絶対やらない方針で、第三者の4名の先生方にオープンで委員を選んでもらうことにしました。それと事務局は民間のシンクタンクに依頼して、情報公開の徹底を図った。淀川(流域委員会)の最大のポイントは原案を国交省が作成しないことでした。国交省が原案を出すと結論ありきになる。でも住民の方々にも別の結論があるわけです。そうなると最初から賛成反対で議論にならない。ですから淀川では原案なしのゼロからのスタートで皆で議論してゆくことにしました」
そうした議論を進めていったことで、役人も学者も住民も、それぞれが変わっていったと宮本さんは言う。
「(淀川流域委員会には)ダム賛成推進派のガチガチの御用学者もおりました。ところが現地へ行って、そのあとみんなで酒を飲んでたら、魚のことを知っている専門家、漁師さん、農民の話を聞いて『環境のことを考えたらダム推進なんて言っていられない』と言い出したんです。それほど変わられたんです。別にその先生だけじゃなくてみんな変わった。私も変わりました」
しかし画期的と思われた淀川流域委員会も、今や従来治水へと逆戻りしてしまっているという。
「住民意見の反映ではなく住民対話の拒否に戻ってしまいました」
運用から30年もの歳月を有しても河口堰のゲートが開放されないのは、逆戻りした河川行政の頑なな姿勢にあるのかもしれない。国土交通省と水資源機構が会場に足を運ぼうとしない現状を見ても、住民との対話について消極的であることを物語っている。
下記の記事でも同シンポジウム後半の内容をお伝えする。

※このページは『つり人 2025年10月号』の記事を再編集したものです。




.jpg)
.jpg)
%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-1.jpg)

-1.jpg)

-1.jpg)

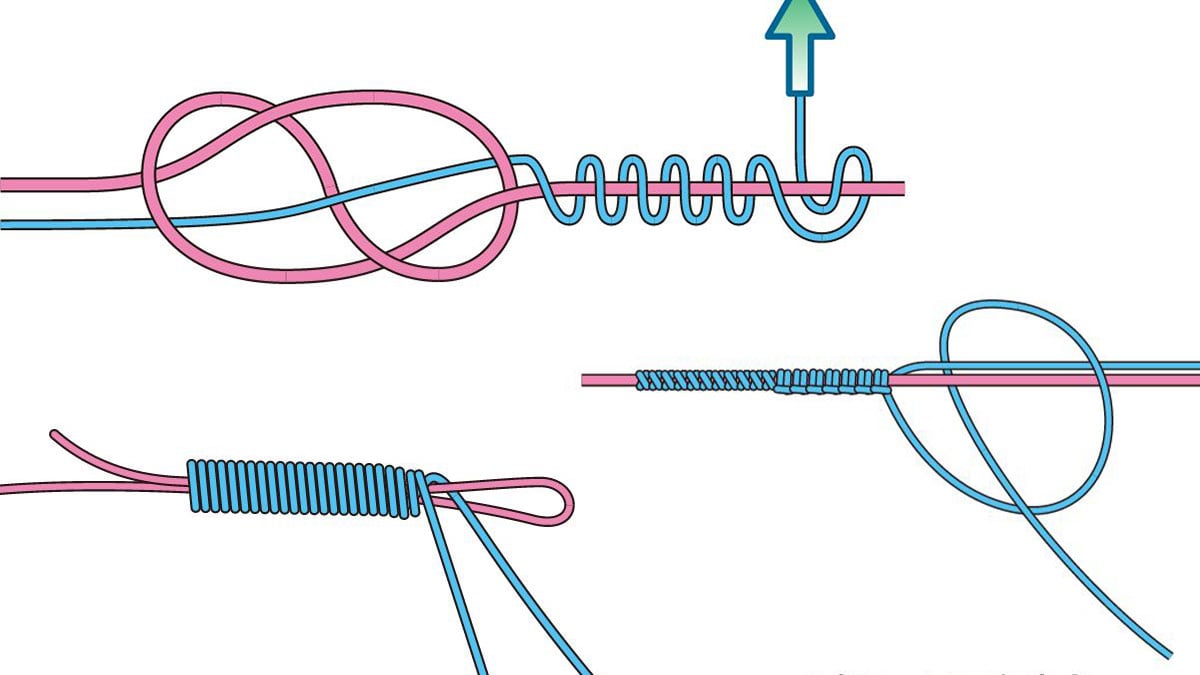

.jpg)

.jpg)





.jpg)
-Mar-10-2026-02-12-50-0678-AM.jpg)





.jpg)
.jpg)

