昨今のようにトラウトルアーのバリエーションが充実する以前、川でもメタルジグを使って釣果を上げていたアングラーは少なくなかった。では、川でメタルジグがハマる条件とは?シチュエーション別にみてみたい。
Photo & Text by North Angler’s
North Angler’sとは?:北海道での釣りを満喫するための情報誌。北海道の自然を体感するキャンプの情報や、フィールドを守るための環境問題にも光を当て、多角的な視点からアウトドアライフを提案している。誌面と連動したウェブサイト『つり人オンライン』での記事展開に加え、好評放送中の『ノースアングラーズTV』や公式動画チャンネルである『釣り人チャンネル』を通じても、北海道の釣りの魅力を発信している。
目次
河川のトラウトフィッシングでメタルジグは使える?
ジグといえば海岸や湖沼といった広大なフィールドで飛距離を伸ばすイメージが強いが、河川のトラウトフィッシングでも持ち味を活かすことができる。河川でも遠投性の高さは魅力だが、沈下スピードの速さに着目するアングラーが多いようだ。
シンプルな形状のメタルジグ(以下ジグ)は、速やかに底に届けられるのが利点。同じメタル素材で作られたスプーンでも底を釣ることはできるが、カップやカーブが付いて水の抵抗を受けやすく、ジグと比較すると沈下スピードは遅くなる。それなりに水深と流れがあると、底まで沈めるのは意外に難しい。スプーンは着底までに長い助走距離が必要になる一方、流れの影響を受けにくいジグは短い助走で届けられる。流れの速い河川で試すと20gのスプーンより15gのジグのほうが速く底に到達する。
冬こそ輝きを増す
そんな特性を持つジグが、シーズンを通じて最も活躍するのは冬だろう。水温の低下とともに魚の活性は低くなり、低水温に強いアメマスでも底に張りついて動きが鈍くなる。よほど条件がよくない限り、ルアーを追って食うことは少なく、魚の鼻面までルアーを届け、アクションを加えて食い気を誘うのが常套手段。そこでジグの出番というわけだ。
メタルジグでのシチュエーション別攻略法
では、川でジグがハマる条件はどんな場面だろうか?シチュエーション別にみていこう。
湿原河川
昔も今も河川のトラウト向けに作られたジグは少なく、ブラックバス用やメバル用が使われてきた。前者は、扁平な形状でハンマード加工が施された『ホプキンス ショーティー』などがよく知られ、以前から冬の釣りで実績が高かった。ウエイトは14g前後で、軽比重素材を採用しているルアーが多い。
このタイプはリフト&フォールが有効だが、巻いても動きがよく、縦と横どちらの誘いにも対応する。何よりフラッシングのアピールに優れ、とくに透明度の低い湿原河川のアメマスねらいで効果が伝えられた。岸近くから深く、いたるところに障害物のある湿原河川では、古くからジグが活躍してきた。ゆったりと流れているようで実は押しが強く、ポイントのスペースは狭いことが多々。そんななか、短い助走距離で底に届けられるジグが重宝するのは想像にかたくない。
操作はロッドを立ててリフト&フォール、またはボトムバンピングが基本。扁平なタイプのほか、より底のとりやすい棒状のジグも好まれた。このタイプは流れと障害物が複雑に絡むポイントで頼りになる。いずれにしても底をダイレクトに探ることになり、フックをテールに装着すると根掛かりが頻発する。極力ロストを抑えるには、ヘッド部にスイミングフックを付けるアシストフックのシステムが好適だ。
%20(2).jpg?width=1280&height=720&name=P044-045-02%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(2).jpg)
渓流域
メバル用ジグは小型軽量で5g前後のラインナップが中心。足場の高い港や磯からのアプローチを前提に開発され、フォールアクションを重視したタイプが多い。そのサイズ感と特性からマッチするのは渓流域。流れの緩いプールや、落ち込みの直下などをねらうのに向いている。
昨今の進化したヘビーシンキングミノーなら渓流域で底を探るのは容易だが、何といってもジグはコンパクトという点で分がある。水生昆虫をイメージできるほどのシルエットゆえ、ミノーにスレた魚が興味を示す可能性があるだろう。何を投げても反応がないという場面を想定し、ケースに入れておいて損はない。
.jpg?width=1280&height=720&name=P044-045-01r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
サケ稚魚パターン
前出のメバル用ジグのなかには、棒状で細身のシルエットが際立つタイプもある。そんなジグが威力を発揮するシチュエーションとして、サケ稚魚が見られる春の本流域が挙げられる。サケ稚魚の降海が始まると、アメマスなどのトラウトは行動をともにするように流れを下り、ときに川が沸騰するようなボイルが見られる。
イージーに釣れる気がするが、難易度はけっこう高め。サケ稚魚を偏食しているトラウトは、サイズ感がマッチしたルアーでないとなかなか食ってこない。しかも、フィッシングプレッシャーが高いと、ボイルやライズは岸近くではなく、遠くで起きることが多い。そこでジグの出番となる。
棒状のジグで実績が高いのは、鉛筆のように細い本物と似ているせいもあるだろう。が、それだけではなく、「泳いでいるのか?」と思うくらいの弱いアクションがハマるようだ。この動きこそ本物に近く、かつ魚をスレさせないと考えられる。最近は小型の棒状ジグが少ないが、サケ稚魚の時季には強い味方になってくれる。操作は表層でのタダ巻きを基本に、ときおりスピードに緩急をつけると効果的だ。

大河川
石狩川や天塩川、十勝川といった大河川の本流域は、ミノーやスプーンだと対岸に届かない場所がほとんど。こんなシチュエーションでは、ジグの遠投性の高さをフルに発揮させたい。海アメ&海サクラで使われる28g前後を使い、手前のポイントは捨てて対岸寄りを中心に釣る。キャスト後は底をとり、リフト&フォールやボトムバンピングで探る。うまいぐあいに地形が変化するスポットに到達したらヒットチャンス。底がとれないほど流れが強ければ、ドリフトさせてねらうとよいだろう。
以前にNorth Angler’s本誌(2024年12月号)『大ものハンターの心得』で登場いただいた鎌田浩明さんは、ジグのドリフト釣法で好釣果を上げている。「流れに負けずしっかりと探れる分、重いジグで誘ったほうが有利」と話し、60gのジグも投入する。この重さになるとタックルが限定されるとはいえ、新たなメソッドとして要注目だ。
工夫を凝らしたトラウトルアーが数多くある今、あえて他魚種用に作られたジグを投入する必要性は薄いのかもしれない。しかし、使っている人が少ないということは魚が見慣れておらず、興味をひきやすいともいえるのではないだろうか。この冬、川でもジグを投げてみたい
.jpg?width=1280&height=720&name=P044-045-04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg?width=1280&height=720&name=P044-045-03%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)

.jpg)



%20(2).jpg)
.jpg)
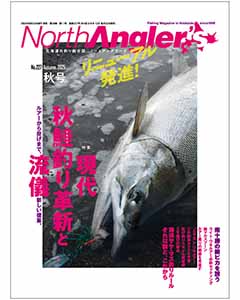



.jpg)
.jpg)




.jpg)




%20(2).jpg)

.jpg)

-Jan-29-2026-05-55-50-2703-AM.jpg)





.jpg)

