回遊ルートを見つけることを重視しがちなウエーディングでの干潟の釣り。 しかし、シビアな状況ではそれに加えて流れを正確に捉えてルアーをイメージとズレなく流せるかが肝要となる。今回はウエーディングシーバスの釣り方のコツをエキスパートの川上靖雄さんに聞いた。
写真と文◎編集部
ウエーディングシーバスの魅力
「ウエーディングをする人は総じてシーバス上級者だと思います」 そう話すのは湾奥や房総半島をホームにシーバスを年中追いかけている川上靖雄さん。ウエーディングは装備や技術面も含めてオカッパリと比べて誰でも手軽に、というわけにはいかないが、やっぱりウエーディングが一番面白いと言う。
「当然オカッパリもするんですけど、ほとんどウエーディングしていますね。オカッパリだと視覚でしか情報が得られないじゃないですか。でもウエーディングは浸かっているから水温だったり流れの強弱を体で感じられるんですよ。何より魚との距離が一番近い釣りです。寄せてきた魚が派手にエラ洗いしたら飛沫が顔に飛んでくるじゃないですか。あれが好きなんです」
.jpg?width=1280&height=720&name=06_DSC_5117%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
流れの変化を掴むための「タックル」と「アプローチ」
10月上旬の後中潮3日目に下げ潮のタイミングで川上さんが向かったのは小櫃川。千葉県内では養老川と並んで人気のウエーディングスポットである。どちらも河口から干潟が続いているが、なかなかそういった環境は少ないという。この日は北風が吹き、アクアラインの風速計では8mとなっていた。加えて小雨も吹き付ける状況のため、川上さんは風を背負って釣りができるように右岸側からエントリーした。
必ずしも遠投は必要ない
ウエーディングというとオープンエリアで遠投というイメージが強いが、必ずしもそうとは限らないという。
「今日は小櫃川の川筋をねらいます。掘れているので魚の通り道になっているんですが、フルキャストしなくても対岸側に届いてしまうほどの距離感です。その中で、どこに魚が付いていてどうねらっていくのかイメージができていないとシビアな状況で魚を出すのは難しいです」
小櫃川河口を沖合に向かって歩いていくと番小屋が建っている。まずは番小屋の少し沖合から探ってみる。対岸側には何人かアングラーがいるようで、ラインがクロスしないように気を付けながら投げていく。最初に選んだのは水面を引くカウンターウェイク120F。続いて水面直下に入るモニカ125F、サイズダウンしつつさらにレンジを下げるためにシンペンのワイゾン80Sとルアーを交換していく。ワイゾンだと底を擦るようでモニカ125Fに戻す。ベイトは見当たらないが、いい具合に流れは利いているようだ。
.jpg?width=1280&height=720&name=02_DSC_5247%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
流れの向きを考えながら釣る
干潟の流れというのは河川ほど流れが一方向を向いていない。立ち位置が変わると同じ方角に投げたとしても流れの向きが少し変わっている可能性が高く、これを正確に把握できていないとイメージと実際のルアーの流し方が乖離してしまう。クロスで流しているつもりが実際はダウンで流している状態となっていれば、知らず知らずに魚から遠ざかることになってしまうわけだ。
流れがどの向きを向いているか、利いているかどうかを把握することは、流す釣りであるシーバスねらいにおいて状況判断に欠かせない情報のひとつである。
.jpg?width=1280&height=720&name=05_DSC_5087%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
【25エクスセンス】軽量ローターがもたらす「感度」のアドバンテージ
この日、川上さんが使用していたリールは25エクスセンス3000MHG。樹脂製の軽量ローターが採用されており、巻きが非常に軽いため、流れの変化が巻きの重さに反映されやすい。そのうえボディーはフルメタルとなっているため剛性も充分。「流れを感じ取れる繊細さとランカーとのファイトにも負けないパワーを持つシーバス専用機としての理想形になっていると思います」と川上さんも太鼓判を押す注目のリールだ。
.jpg?width=1280&height=720&name=03_DSC_5082%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
【川上さんのタックル】
ロッド:エクスセンスジェノスS96M/RF
リール:25 エクスセンス3000MHG
ライン:PE0.8 号
リーダー:フロロカーボン20 ポンド
アップクロスで流し込み70cmオーバー捕獲
「なかなか回遊してこないので、番小屋の正面まで戻りましょう。番小屋の脚周りがストラクチャーとなっているので、そこにシーバスが付いているかもしれません」
川上さんは流れに対してアップクロスでキャスト。ドリフトでモニカ125Fを流し込んでいき、小屋を過ぎた辺りでルアーがターンすると一発でヒットした。良型ならではの重いエラ洗いの音が聞こえる。ここは土砂流出を防ぐためのシートパイルがライン状に伸びており、カキ瀬となって海底に沈んでいるため、川上さんは慎重なやり取りで寄せてくる。水飛沫を被りながらランディングした70cmオーバーは丸々としており、川上さんもガッツポーズ。その後、追加をねらったが、潮止まりのタイミングで良型マゴチをヒットさせて納竿となった。
.jpg?width=825&height=850&name=13_DSC_5167r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
ダウンクロスだけでは獲れない魚がいる
「広い場所でのウエーディングではダウンクロスでしか探らない人も多いですが、それだと反応しない魚もいます。干潟でも流れに対してさまざまな角度でアプローチすると難しい状況でも魚と出会うチャンスは増えますよ」
ここ数日、県内の各河川でサオをだしてきたという川上さんだが、どこも状況は芳しくなかったと言う。そんな状況で反応を得るにはルアーサイズを落とすことも効果的だ。これからの季節は河口・干潟だと12cm前後のシャローランナーが主力となるのは間違いないが、そのルアーサイズには口を使わないことも割とあるという。流し方の工夫で反応がない場合は、河川の明暗や港湾部で使うような8cmクラスのミノーやシンペンを投げると途端に反応することも多々あるのでお守りとして用意しておき、秋のパワフルなファイトを楽しんでほしい。
.jpg?width=1280&height=720&name=07_DSC_5283%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
.jpg?width=1280&height=720&name=08_DSC_5281r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
.jpg?width=1280&height=720&name=09_DSC_5286%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
※このページは『つり人 2025年12月号』の記事を再編集したものです。

.jpg)





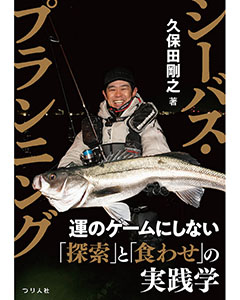







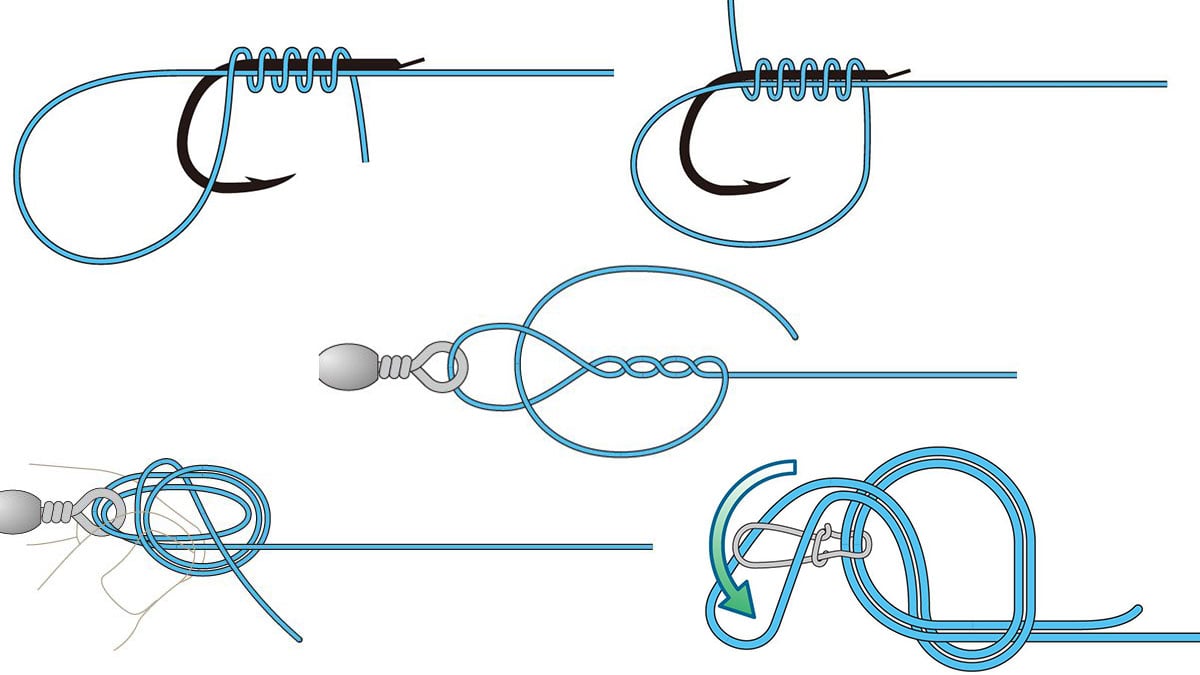


%20(2).jpg)

%20(2).jpg)







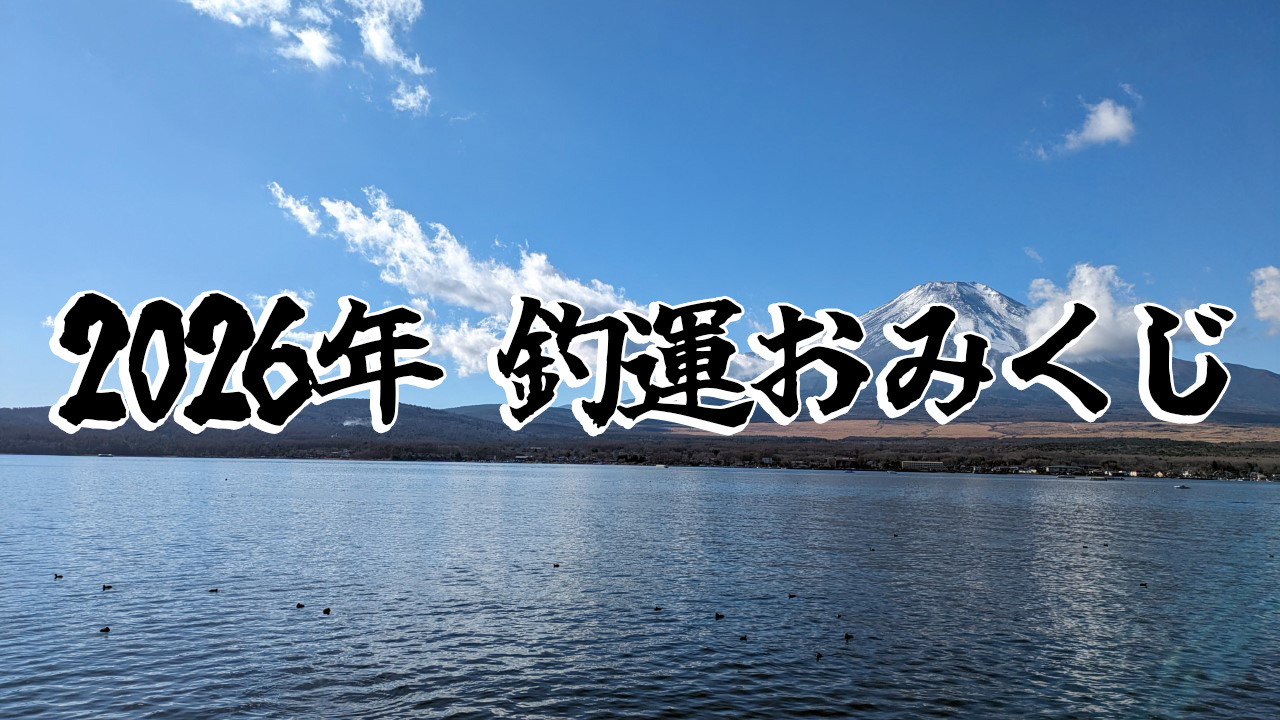
.jpg)


.jpg)
-Dec-26-2025-01-00-45-5413-AM.jpg)


