夕暮れ時の涼しさを感じるころから、川のスズキ釣りは盛期を迎える。 一年のうちで最も数・サイズともに釣果に恵まれる時期の始まりだ。 なかでも秋の象徴ともいえる落ちアユに絡んだ釣りの基礎的な考え方を解説。
文◎工藤靖隆
写真◎編集部
シーバスの落ちアユパターンとは?
そもそも、落ちアユとは何なのか。アユは1年で死んでしまう年魚である。夏の間、成長するために上流域へ遡っていたアユが、秋になると産卵に適した砂利底を求めて下流域へ集まる。この現象が落ちアユと呼ばれるものだ。さらに産卵行動で弱り、流されるアユを、スズキが捕食をする。この状況をシーバスアングラーは落ちアユパターンと呼んでいる。
「落ちアユとは産卵で弱って流される姿のことではなく、下流の産卵場所へ集まるアユ」ということが大切だと私は考えている。 落ちアユが集まる下流域の瀬とは、スズキが生息するエリア内では上流域となる。そもそも冬の低水温期を除いてスズキは川にいるのだが、河川状況によって生息域はかなり異なる。また、冬に海へ下ったスズキは同じ川へ帰ってくる傾向が比較的多い。
友人がとある河川でタグ&リリースによって集めた膨大なデータを見ると、3年連続で同じ河川の同じ橋脚で釣られる魚もいた。ちなみにこの個体は、冬には海でも釣られた記録があり、一生をその川のその位置で過ごしている訳ではない。憶測で語られることの多い川スズキの生態ではあるが、データで見るとアユを追いかけるように、春から川に入る個体が増え始め、秋が深まると下流へ集まり、冬には海へ出ていくことが多い。
スズキは冬に産卵を行なう。秋の深まりと共に始まる落ちアユは、捕食も簡単で産卵前のカロリー摂取にうってつけなので、アユの産卵場所である下流の瀬にスズキが集まってくると考えられる。
.jpg?width=1280&height=720&name=02_DSC03056%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
毎年同じエリア・タイミングで狙いやすい
リバーシーバスとも言われる川のスズキ釣りの中でも、純淡水域で干満による水位の変動がないエリアで1年釣りをしていると、魚がいる・いないのタイミングが非常にはっきりしていることが見えてくる。
川は、同じ時期に同じ状況となることがとても少ない。そのため、毎年情報をリセットして新しく積み上げることが必要で、生息数が多く地形や状況が安定している汽水域に比べると、通わないと難しい釣りともいえる。それでも地域によって暦と季節の差異が多少あるにせよ、産卵に向けたアユの習性が大きく変わらず、毎年エリアが絞りやすくて概ね同じタイミングで始まるのが、落ちアユパターンのいいところだ。

大潮での実績が高い
関東地方では、9月に入るとアユが産卵場所付近へまとまりだし、10月の最初の大潮(新月満月は問わず)ではすでに瀬で産卵行動が見られ、11月の大潮では終息へ向かう。 なお、これは潮回りと太陽暦の組み合わせなので、年によってはひと潮ほどのズレが稀に生じる。釣り人は季節を太陽暦で捉えて動くが、魚は環境の変化によって次の行動が決められていく。落ちアユでも、なんか今年は遅いかな?と感じたら、その年の季節の進行をちょっと思い浮かべてみて、集中して釣りに行く期間を少し修正するとよい。
では、最も釣れる日はいつなのだろうか?実績を見るとやはり大潮でよく釣れているものの、それ以外の潮でも案外釣っている。大潮の実績が高いのは、釣行回数が多いからだけかもしれない。 なお、スズキは「ここで今年も落ちアユが食べられる」と予測して、毎年そのポイントへ集まるわけではない。安全かつ簡単に捕食できるベイトを求めて移動を繰り返した結果そのポイントにたどり着いただけである。そこに来たスズキは「産卵で弱って流されたアユしか食べないのか?」と考えた時、決してそんなことはないと思うのだ。
基本の釣り方は「ルアーの頭が下流へ向くように流す」
産卵が始まり、弱ったアユが流れ出せば偏食する可能性は高まる。これは間違いなく起きることで、バチの釣りと現象は似ている。特定の場所でボイルが繰り返されるのは、明らかにアユが流れてきやすく、シーバスの体力的にも定位しやすいからだ。
この「弱ったアユにつく」パターンは大潮回りでの定番的な釣りで、今までに何人もの名手と全国の河川で釣りをさせていただいたが、皆同じようなことを言うので、ひとつの確立したパターンであることは間違いない。タックルの考えや立ち位置による流し方のキモであるとか、細かい違いはあるが、それは河川状況によるものだと感じている。基本は、とにかくねらいのコースへ「ルアーの頭が下流を向くように流す」こと。
要するに、テンションを掛けすぎるなと皆が口をそろえて言うのは、流れを横切らせず流し込んでルアーを見せていく釣りであることを意味している。 このパターンはスズキが視覚に頼って捕食する傾向が強く、流されるルアーを追尾する時間が比較的長いのが特徴だ。そのため、上流へルアーを入れて定位しているポイントを通過させ、追尾に入ったスズキに、ウエイトの戻りで発生する姿勢変化やトレースコースの変化などで捕食のきっかけを作りだす釣り方が有効となる。
流れを横切らせずに、流れに沿ってルアーを流していくことが大切で、このやり方にマッチするルアーが、落ちアユルアーとよく言われる。重心移動モデルで比較的大きめ、浮力の強いものが好まれる。

落ちアユパターンのルアーカラー
視覚情報重視となると、ルアーのカラーが気になるアングラーも多いだろう。普段のシーバスねらいだとカラーの影響は、サイズ・アクション・コース・レンジ・速度などよりも優先順位は低いと考えている。ただ、ある条件の時だけはカラーの違いを強烈に感じることがあり、そのうちのひとつが弱ったアユにつくパターンである。
30年前から、落ちアユパターンは白か黒を満月と新月で使い分けるのがよいとされてきた。これに近年人気のチャート系も効果的と言われだしている。実際に私も、チャート系でかなりよい釣りをさせてもらっているのだが、ひとつ気が付いたことがある。それはチャートも白も黒も、クリアトップコートがされていないほうが好反応ということだ。使い古されて小傷で艶がなくなったルアーもこれに含まれ、何かしらの理由でトップコートの光沢を嫌うタイミングがあるようだ。ただし、これがすべての河川で当てはまるかというと、確証は全くない。水色や光量なども影響しているはずなので、少し意識してみると面白いと思う。

ルアーの流し方は状況に応じて変える
この時期のスズキは、かなり大きな水位や水温の変化が起きたり、瀬に集結しているアユが消えたりしない限りは、日中に身を隠せる影や深さと、日没後にアユを捕食するポイントのかなり狭い範囲でしか移動しない。他の時期よりもかなりエリアに固執している印象が強い。大潮に限らずとも、産卵のために流れを下るアユがあれば、その近くに必ずスズキはいる。弱ったアユが流れ始めると偏食する傾向が強くなるだけで、スズキは落ちアユ以外のベイトも捕食対象としている。
このようなスズキをねらうには、少し釣り方を変える必要がある。大潮では流れに沿ってルアーを漂わせていくのに対し、アユが流れていないタイミングでは効率よく広めに魚を探していくとよい。流れが当たる岸際だけではなく、その手前のシャローやストラクチャー回りなど基本的な捕食ポイントも、流れを横切らせるようにルアーを通していく。この場合のルアーチョイスは、通常のミノーやバイブレーションなどがおすすめ。
ダウンクロスでねらう場合もあれば、流れを高速リトリーブで横断させながら、ピタっと止めて食わせることも有効だったりする。大潮なのに思ったよりアユが流れていない場合にも効果的なので、落ちアユの釣りであってもいろいろと準備しておくとチャンスは高まるはずだ。
最後に、長く釣りをしてきて思うのは、河川上流域のスズキが減ってきているということだ。もちろん、それらが全てアングラーの漁獲プレッシャーというわけではなく、河川環境の変化や堰などの影響も大きいと思う。ただ、河川のスズキ釣りを楽しむのなら、少しだけ資源のことも考えてほしい。それは、なぜスズキがこんな河川の上流までやってくるのかを考えることに繋がり、パターンにはめ込むだけではないこの釣りの面白さを広げていくきっかけにもなるはずだ。

.jpg?width=567&height=850&name=10_DSC03067%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
※このページは『つり人 2025年12月号』の記事を再編集したものです。






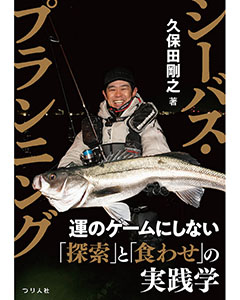





.jpg)

.jpg)


.jpg)




%20(2).jpg)


.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

