シーバスは地形や流れ、水位の変化を利用して狩りを行なう。 ベイトを追い込みやすいシャロー(浅場)は絶好の狩場であり、高活性な個体が回遊しやすい。東京湾奥でシーバス釣りを学んだ久田智司さんは、荒食いの秋こそシャローが激アツと語り、「待つのではなく、動いて探す釣りこそが醍醐味だ」という。今回はそんな久保田さんに、シャローでのシーバスの狙い方をメインに、東京湾奥河川全体で共通する秋のシーバス戦略を解説していただいた。
写真◎編集部
文◎久田智司(ひさだ・さとし)
1998年生まれの27歳。東京都墨田区在住。シーバスゲームとタナゴ釣りを愛する年間釣行300日の理論派アングラー。
秋の東京湾奥シーバスゲームは状況がめまぐるしく変わる
秋。夏の熱気が引き、水温が安定してくるこの季節。東京湾奥のシーバスゲームは、一年の中で最も熱を帯びる。 気温と水温のバランスが整い、沿岸部には多様なベイトが寄ってくる。スズキの活性は一気に高まるが、反面、ベイトの種類もレンジも複雑化し、潮や風、流れの変化によって状況がめまぐるしく変わる。
このため、闇雲にルアーを投げても結果にはつながらない。「魚の位置を読む」「ベイトを読む」「流れとレンジを読む」。この3つをどれだけ正確に掴めるか、状況に合わせて即断即決で動けるかが釣果を左右する鍵となる。
本記事では10月上旬に行なった多摩川での実釣取材をベースに、東京湾奥河川全体で共通する秋のシーバス戦略を整理していく。
ポイントの選び方とアプローチ方法
まず注目すべきは汽水エリアである。潮汐、降雨、気温差、河川流入量など多様な要素が複雑に絡み合い、水質・塩分濃度・流れが刻々と変化する。下げ潮時は淡水流入が増え塩分濃度は下がるが、上げ潮時は海水が河川内に押し戻されて汽水域が拡張する。こうした淡水と海水が混ざり合う汽水域にはベイトの通り道となる場所が多く、シーバスも回遊しやすい。 そこで私は具体的に次の点を意識して汽水域のポイントを選ぶ。
・浅くて緩やかなカーブ部:流れが緩む入口として魚が入りやすい
・橋脚やストラクチャー脇のヨレ:流れの本線との境界に魚が定位しやすい
・砂+泥混在域:ベイトが溜まりやすい
・風裏:風によるベイトの偏りを読み、風裏ポイントを使う
-Nov-12-2025-03-18-04-2774-AM.jpg?width=1280&height=720&name=04%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-12-2025-03-18-04-2774-AM.jpg)
高活性なシーバスがねらえるシャロー帯がねらい目
私は時間帯やベイトの種類に関わらず水深20〜100cmのシャロー帯から探る。ベイトが豊富なシャロー帯は高活性なシーバスが捕食しやすいエリアだからだ。潮位変化に応じて、またストラクチャーの配置を意識して立ち位置を移してラン&ガンする。サッパやコノシロといったベイトを効率よく捕食できるポジションを想像しながら探るのだ。
当然、河川によって魚のポジションは異なる。たとえば旧江戸川では古くから残る地形変化、流れの変化が出やすいエリアで魚をねらうと釣果が出やすい。一方、荒川や多摩川では、橋脚等の人工構造物でできる流れのヨレや浚渫によって形成された地形変化でベイトを待ち構えているケースが多い。
-Nov-12-2025-03-11-59-0505-AM.jpg?width=1280&height=720&name=02r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-12-2025-03-11-59-0505-AM.jpg)
日中の下見も重要
秋になると私は昼夜問わず釣行頻度が多くなるが日中は主にサーチに時間を費やす。風向き、ベイトの動き、次の潮回りにどうなるかを俯瞰的にチェックし、夕方以降のタイミングに備える。夜明け前から朝マヅメにかけて入ることもあれば、夕方~夜のみを集中して釣る日もある。常に「今、魚はどのエリアで、どのベイトを意識しているか」を予測しながらルートを構築することが、秋の釣行では不可欠となる。そのためには水面に出るベイトの波紋や反転をしっかりと観察し、逃げ惑うようすがあれば即座に反応したい。
同じポイントでも時間帯ごとにアプローチを変える
また、秋は昼夜の寒暖差が大きく魚の行動リズムにも変化が出やすい。朝夕のマヅメ時に動きの活発な個体と、夜間の静かな流れを好む個体とが混在するケースも少なくない。言い換えれば「時間帯ごとの捕食スイッチ」を読み切る力も必要になってくる。秋のシーバスは、朝は浅場、日中は深場の中層近辺、夜は再び浅場へ戻る傾向があるので、時間帯によって同じポイントでもアプローチ角度やルアーを変える柔軟性を持つこともまた有効だ。
ではどんな時合にシーバスの活性は高まりやすいのか?キーワードは「変化」である。特に潮が変化する前後10分に活性が高まることが多く、中でも潮止まり直前の潮が緩む瞬間の10分は最大限の集中力で挑みたい。
-Nov-12-2025-03-17-32-6952-AM.jpg?width=1280&height=720&name=05%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)-Nov-12-2025-03-17-32-6952-AM.jpg)
3種のベイトパターンと時合
10月から11月にかけてのベイトはイナッコ、サッパ、コノシロの3種が主要になる。これらを追って中~大型のシーバスが河川にも差してくる。それぞれのベイトが棲み分けるレンジや行動特性を理解し、ルアーを使い分けることが釣果の鍵となりうる。回遊ルートを読んで捕食のタイミングをねらい撃ちする。
イナッコ
9〜11月にかけて最有力となるパターン。小型イナッコが河川内を漂い、表層~中層に広く散る。このレンジで口を使わせるには、リトリーブ速度を抑え、流れに乗せて自然に漂わせる意識が必要。見せすぎず、引きすぎず、あくまで漂わせることを重視する。そのため、ハグレ96Fといった動きが強すぎず、スローに引けるルアーが効きやすい。

サッパ
9〜11月を通じて安定して発生するベイト。中流・運河部域でよく見られ、群れを形成しやすい。明暗部、ヨレ、流速変化帯に溜まりやすい性質があり、ルアーは若干レンジを下げ、間を持たせたアクションで誘うことが重要だ。強い動きのルアーでは魚が見切ってしまうシーンが多く、ハグレ96Fやツクモ56/66のように弱めの動きが刺さる場面が増える。サッパパターンでは、明暗部でのボイルが高頻度で発生することもある。東京湾奥河川では、条件が整えば一晩で数十尾の釣果を叩き出すことさえある。

ジャッカル ジナリ65(写真左):根掛かりを回避しつつ中層を探れるバイブレーション。流心部や中深域でレンジを落として探る際の保険ルアーとして重宝する。

コノシロ
秋後半から強さを増す大型ベイトだ。コノシロが岸近くへ群れをなして接岸するようになると、大型のチャンスが一気に高まる。ただし群れに着く魚はスレ感が強く、ルアーを見切ることも多い。アピール力と違和感のない挙動のバランスが求められる。存在感を持たせつつ泳ぎが破綻しないルアー選びが、釣果を分ける。
これらルアーのカラーローテーションとして、光量の少ない釣り場や濁りが濃い状況ではレッドヘッドやチャート、澄み潮や満月の夜はクリア/ナチュラル、また大型ねらいとして黒もよく使う。満月、新月、街灯や橋脚灯の影響で水面照度はガラリと変わる。水質や濁り、ベイトカラーに応じたカラーを選択すると深いバイトを得られるようになる。

秋のシャローゲームでは、流れの変化とレンジ精度こそがすべて
10月の上旬に多摩川に実釣。夜の気温は21度前後。水温はやや低下傾向にあった。河口域のシャロー帯をウエーディングで探っていく。満月の大潮で光量が多く、魚にプレッシャーを与えすぎないよう慎重に展開した。ねらいは干潮間際。流れが緩む一瞬の時合をねらい撃つ。イナッコが追われて騒ぐ場面があったがルアーには当たらない。そのまま干潮時刻を迎えた。
上げ潮に転じたタイミングで橋周りに移動して明暗部を探るもベイトっ気が皆無。魚の付く可能性が薄いと見て、さらに上流のシャロー帯へエントリーした。 砂泥底が広がる浅場と、僅かな起伏があるブレイクライン、そしてゆるやかなカーブ部が混在する典型的なベイト集積エリアである。潮位が上がるにつれて、浅場へ魚が入り込んでくることを想定して釣りを組み立てた。
まずはハグレ96Fで水面直下を丁寧に探るが反応なし。時間が経過し、潮が動き始める気配を感じてハグレ120F(取材段階ではプロト版、2025秋発売予定)に切り替え、流れに同調させてブレイクに落とし込むアプローチにシフトすると、潮目で「ゴンッ!」という鋭いバイト。魚は水面を割って跳ね、強い走りを見せた。
この日のポイントは、「流れが出始めた瞬間」と「浅いヨレとの境界」。秋の河川では、流速変化に魚が反応する時間帯が非常に短い。このためルアーローテーションも、アプローチの切り替えも、即断即決が勝利を呼ぶ。鮮明に感じたのは、「秋のシャローゲームでは、流れの変化とレンジ精度こそがすべて」ということだ。ルアーは浅層レンジをキープしながらも存在感を出すバランスを持ったものが強く、それがなければ見切られてしまうことが多い。
ハグレ120F(プロト)は、まさにそのバランスを持つルアーであり、河川シーバスにおける必須ルアーになりうる可能性を強く感じた。また併用したハグレ96F、ツクモ56/66、ジナリ65のローテーションが状況対応力を高めてくれた。 東京湾奥の秋は毎日表情を変える。潮、風、ベイト、光量。そのすべてを読み、即座に反応できるかどうかで釣果が決まる。待つのではなく、動いて探す釣りこそが秋の醍醐味だ。


※このページは『つり人 2025年12月号』の記事を再編集したものです。


-Nov-12-2025-03-57-16-9646-AM.jpg)









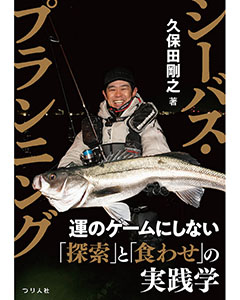





.jpg)

.jpg)


.jpg)




%20(2).jpg)


.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

