秋イカは誰もが気軽に楽しめるはずだった。 だが、年々難易度が高くなっているのは気のせいか。 そんな局面を打破するには、違和感をなくしすべての工程をナチュラルに……という考えは捨てたほうがいいかもしれない。本記事では和歌山県・南紀エリアへの実釣を通して、エギングのエキスパート笠松仁さんが実践するアクションとその思考法を紹介する。
秋イカは誰もが気軽に楽しめるはずだった。 だが、年々難易度が高くなっているのは気のせいか。 そんな局面を打破するには、違和感をなくしすべての工程をナチュラルに……という考えは捨てたほうがいいかもしれない。本記事では和歌山県・南紀エリアへの実釣を通して、エギングのエキスパート笠松仁さんが実践するアクションとその思考法を紹介する。
写真と文◎松本賢治
解説◎笠松 仁
笠松 仁(かさまつ・ひとし)プロフィール:和歌山県南紀がホーム。エギングをメインにライトゲームまでシーズンに応じて濃厚に毎週末、楽しんでいる。和歌山県在住
秋エギングはスキルアップに最適
秋イカと聞けば、シャローで手軽にサイトフィッシングが楽しめるシーズンというイメージが浮かぶ。一方、春の大型イカも産卵を意識した個体がシャローへ差してくることから、釣りにくい(産卵個体は反応が悪い)とはいえサイトが成立するケースも多々ある。ということで、笠松さんは春イカゲームでのパフォーマンス向上を想定して秋をトレーニングの場として楽しむことを勧める。
「秋の見釣り(サイト)をやっていたら、それが春の釣りでも生かせる。秋は春に比べてイカの反応がいいので、すごく勉強になる。今エギを動かしたらアカンのか、これは動かしすぎなのか……よく見ているとその加減がわかってくる。いろいろアクションを試してみて最終的には不要なアクションを削除していく。サイトでその感覚がわかればブラインドでもできるようになる。秋はいろいろ考えて釣りができるのが面白いですよね」と笠松さんは秋の魅力を説明する。
大きくエギをダートさせたり、強く動かした際イカがバックしたり……そんな経験を皆さんも何度となく味わっているはず。そんなイカが嫌がるアクションを削除していけば、エギを抱く正解のアクションにたどり着けるということ。 ただし、春と秋では当然違いもある。
「秋は新子で好奇心が旺盛なのでイカを追っても釣りが成立しやすい。追うというのは、サイトでねらっている特定の個体に対してキャストする角度やアプローチを替えて何度もねらうこと。もちろん、スレますけど春よりはマシ。春イカは基本的に産卵行動が目的なのでナーバスな状態。何度もねらうほど釣れにくくなるので、一投を大事にしていく。その差は大きいですね」
%20(1).jpg?width=1280&height=720&name=03-kasamatsu-ika-sele-30%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)
秋エギングのアクションで意識したいポイント
笠松さんは、サイトでイカを見つけたら、その個体より最低10mは離したところへエギを着水させ近づけていく。どれもイカの腕側を通すコースだという。
「着水点からイカまでの距離を5mほどまで速やかに近づけたところから、まずはフォールでようすを見ます。秋はボトムを取りません。そして、次はシャクリ上げて反応をみる。(イカのレンジより)下へ入れてどうか、上へ上げてみてどうか……反応を見る。基本的にはフォールで乗ってくるのでレンジは下にはなるんですが、反応させるという部分ではシャクリ上げのほうに分がある。そこがエギとの距離を縮めてくるタイミング。だから、どういうシャクリ上げをするかも大切になってくる。つまり誘い(アクション)ですね。だから、まずはどう誘えるかがキモだと思っています」
当然、状況にマッチした誘いができないと乗せられない。うまく誘えてこそ次の段階であるフォールへ進める。
%20(1).jpg?width=1280&height=720&name=05-kasamatsu-ika-sele-38%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)
シャクリはアピール重視
「秋イカとはいえ、近年の紀伊半島のイカはどんどん賢くなっているので難易度は高め。イージーに釣れる状況は少ないですね」
だからこそ、どうにかしてサイトで釣ろうと考える。たとえ1パイ目がイージーに釣れても後が続かない、というのは常。そうなると、釣り人は本来のエサに近づけようとナチュラルさを求める傾向にある。これは、エギの不自然な動きに警戒しているという考えが前提にある。だが、笠松さんは逆の発想だ。
「〝エギはエギ〞っていう話を聞いたことがあるんです。エギは最初から偽物なので自然界にいるエサに近づけることはできないっていうことです。だから、誘うときは偽物としてとにかくアクションを重視する。それがイレギュラーで人間から見て違和感のあるアクションでも、とにかく誘えればいい。それが誘いとしては正解だと思っています」
どう考えても自然界に存在しないアクションやカラーでも釣れるところがエギを含むルアーフィッシングの醍醐味でもある。ただし、ナチュラルに寄せたほうがいい要素もある。
%20(1).jpg?width=1280&height=720&name=01-kasamatsu-ika-sele-52%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)
乗せるフォールは自然に
偽物としてアピールするのか、ナチュラルに寄せて演出するのか。エギングの場合、笠松さんも乗せるとき、つまりフォールのときはナチュラル側へ寄せるという。
「やっぱり乗るのはフォール。アクションからフォールへ移行させる段階からエギの動きはスムーズに行なわないと抱いてくれない。エギの角度の移行もスムーズに。そして、フォールスピードも等速にしてやるのが理想です。ドロー4は自在にその点をコントロールできるように設計されている。つまりコントロール性能が高いマニュアル操作が可能なエギ。ダート幅も調整できるし、フォール姿勢も変えられる。だから、サイトでイカの反応を見ると同時にエギのコントロール感を身につけるのにも役立ちます」
自分がエギをどう動かしているのか。それがわかればサイトでもブラインドでも思いのまま。もちろん、ドロー4を普通にシャクってカーブフォールさせて使うことはできる。だが、激戦区や激渋の状況を制するには、引き出しは多いほうがいい。イメージ通りにコントロールできるエギは、つまりはあらゆる状況に対応できるわけだ。
.jpg?width=1080&height=720&name=06-kasamatsu-ika-sele-33%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
%20(1).jpg?width=1280&height=720&name=02-kasamatsu-ika-sele-49%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)
フォールのキモは「等速」
取材は8月下旬の南紀。秋はどこでも釣れそうなイメージがあるかもしれないが、そうではない。笠松さんのポイント選びとは?
「秋イカのような小型は夜に大きく移動して、昼はフィッシュイーターから隠れて岩陰などに身を潜めていると思うんです。だから、時間差で入り直すこともあります。逆に誘い出しても出てこない場合、そのポイントは見切ります」
つまり、日中にイカを見つけたエリアやポイントには入り直す価値がある。だから、イカを見つけることを先決する。大きく移動するのもいいが、狭いエリア内を時間差でランガンするのもあり。今回はキロオーバーの夏の残りイカがいるスポットを見つけたため、すさみエリアをランガンする計画となった。
まずは、江須ノ川漁港からスタート。ここは前日のプラでキロオーバーの夏イカの残り組がいたところ。そして、この日も現われた。だが、何をしても無視。見えている小イカの反応も悪い。いることが確認できたら次へ。南下して里野の地磯へ入った。 笠松さんは、さっそく見えイカを見つけアプローチ。フォールするエギを追えばそのままテンションフォールさせるが、追うのを止めた場合は完全にラインテンションを抜いたフリーフォールでスピードを上げて追わせるように仕向ける。テンションフォールではなるべくエギを手前へ寄せたくないためテンションは弱め。とはいえ、カーブフォールから水平スライドへ移行する誘いも織り交ぜていた。
ここで笠松さんが重要視するのは、等速スピードという点。フォールの段階で追ってきているときは終始、等速フォールをキープすることを目指す。そのパターンで笠松さんは200~300gの秋らしいイカをポロポロと釣りあげていく。
%20(1).jpg?width=1280&height=720&name=04-kasamatsu-ika-sele-25%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0)%20(1).jpg)
釣り場に時間差で入り直すのも有効
秋はドロー4の3.0号がメイン。カラーにこだわりはないが視認性の高いものを選んで使っている。
「3.0号で何度も寄ってはくるけど乗り切らないときは最終的に2.5号に落としてやると乗ってくることがある。外海で回遊を潮通しのいい水深のあるところでねらう時は3.5号も使います」という感じ。
時間が経つにつれウネリが強くなり撃てないシャローが増えてきた。大きく北上して江須崎の地磯へ。途中、朝イチに入った漁港へ再度入り、夏イカの残りへ再アピールするも翻弄されただけだった……。
「近年、気難しい秋イカが増えているので、ひとつの条件だけではなかなか釣れない。マヅメ、潮、ブレイク……とかひとつの条件では釣りにくい。例えば、朝マヅメ×潮とか。上げ潮×シェードとか、潮×ベイトとか。なにか+αがないと釣りづらい気がしています。この夏イカもタイミング次第で……とは思いますけど(苦笑)」と笠松さんは常に複合的に条件を探す。
だから、時間をズラしてポイントへの入り直しをする。イカが見えたポイントでは、ほぼ1パイは拾っていくことができた。ポイントをぐるぐる回ればさらに数を稼ぐことができるはずだ。
「実際に紀伊半島全体的にイカの数は減っているように感じます。賢いイカも増えて難しいから腕を磨くのにはいいですけどね。そう、日中はシェードをねらうこともキモになります。大きなシモリの影や磯の影ですね。その横を通してやると出てくることもよくありますから」 と笠松さん。
水温が下がり始める11月中旬から後半まで日中の秋イカゲームでキロアップも期待できる。それ以降は、ナイトのほうが釣果とサイズが出やすくなるだろう。
.jpg?width=1080&height=720&name=07-kasamatsu-ika-sele-36%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
.jpg?width=748&height=850&name=10-kasamatsu-ika-sele-18r%20(%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0).jpg)
※このページは『つり人 2025年11月号』掲載の記事を再編集したものです。

.jpg)

%20(2)-1.jpg)
a-1.jpg)
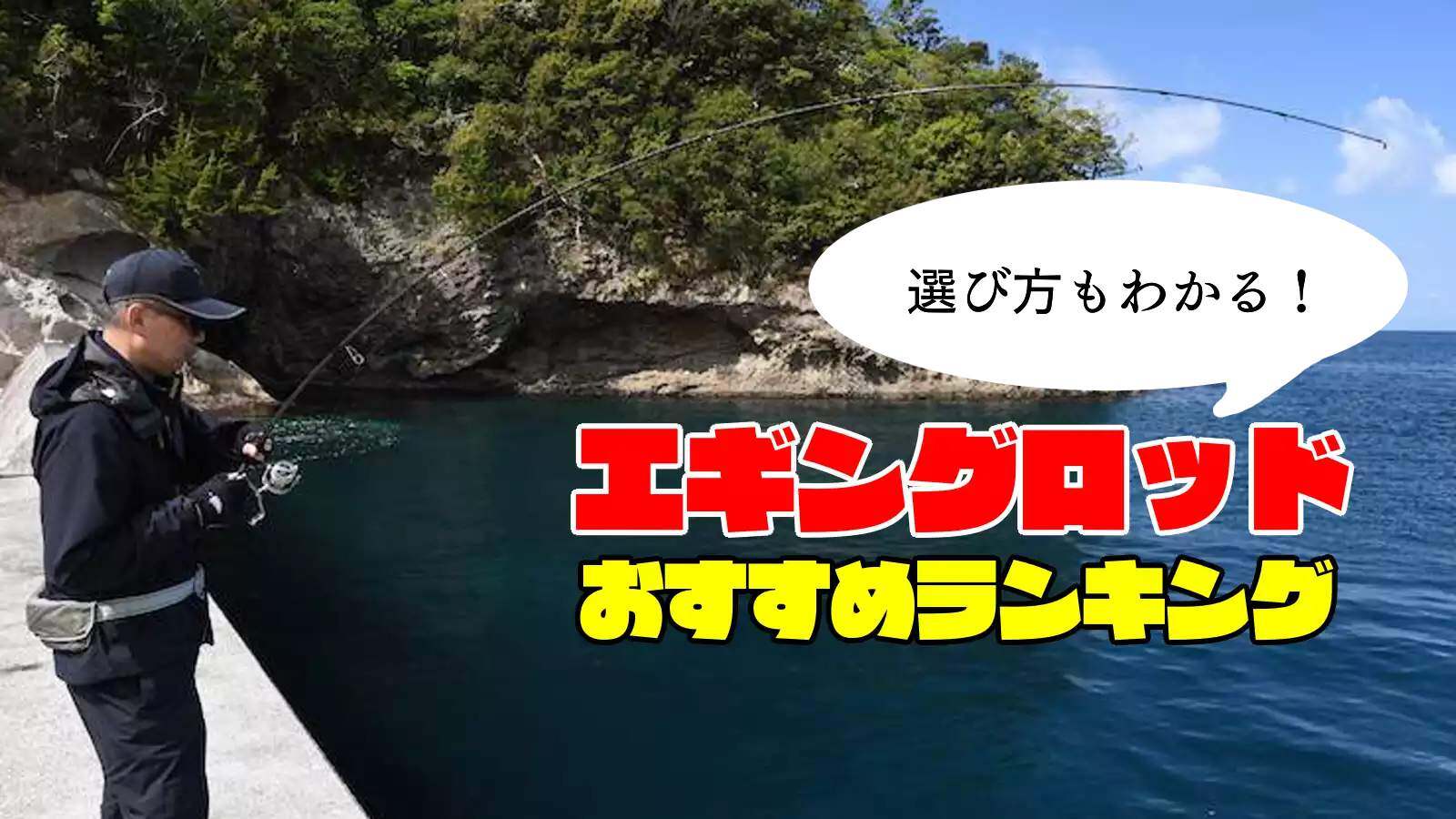







.jpg)


%20(2).jpg)

%20(2).jpg)
.jpg)








.jpg)



