
※10月20日現在。今後参加予定の企業・団体様も決まり次第順次掲載していきます。
■『Basser Allstar Classic』とは?
バス釣り専⾨誌・⽉刊『Basser』が、国内外で活躍するスター選⼿を招待して⾏なう⽇本最⼤規模のバスフィッシング特別招待試合を中⼼とした、釣りとアウトドアの⼀⼤野外イベントです。
会場となるのは千葉県⾹取市の公共施設「⽔の郷さわら」。
メインイベントとなる招待試合のほか、主催者によるチャリティーオークションやビンゴ⼤会、ブース出展する各社による即売会やくじ引き等のイベントが2⽇間にわたって催され、例年多くの来場者でにぎわいます。
2018年⼤会時には家族連れなど2⽇間で約1万5000⼈が来場しました。有観客としては4年ぶりとなる今回はさらに規模を拡⼤。
拡張された出展エリアには釣り業界だけにとどまらず、⾃動⾞、マリン、アウトドア、アパレルブランドなど80以上のブースが⽴ち並びます。
■競技解説
本イベントの中⼼となるのは、実⼒と⼈気を兼ね備えた⼀流選⼿たちによる本気のバスフィッシングトーナメント(⼤会)です。
第⼀回⼤会(1987年)から「湖上で起こっていたことのすべてを公開する」を理念に掲げ、出場全選⼿に記録係が同船するスタイルを守り続けており、観戦スポーツとしての釣り⼤会を確⽴しています。
選⼿たちが釣りをする競技エリアは、利根川下流部の約60kmの流域(千葉県)と⽇本で2番⽬に広い湖である霞ヶ浦・北浦⽔系(茨城県)の全域。
時速100kmの速度が出るボートを1時間以上も⾛らせてポイントに向かう選⼿もいます。
各選⼿が1⽇に釣ったブラックバスのうち、⼤きなほうから3匹の重さを集計して順位を決定。これを2⽇間にわたって⾏ない、最重量を記録した選⼿が優勝となります。
注⽬選⼿のボートにはライブ中継の動画カメラマンが同乗。YouTube「釣り⼈チャンネル」にて、スタジオ解説を交えながら⼀挙⼿⼀投⾜がライブ配信されます。
■バサーオールスタークラシックにおけるデジタルウエイインの導入ついて
今年のオールスタークラシックはデジタルウエイインを採用します。釣ったバスを船上でウエイト計測し、プレスアングラーが現認・記録のうえ、その場でリリースする仕組みです。採用の理由はただひとつ。バスに与えるダメージを極力抑えるためです。
オールスタークラシックの舞台である霞ヶ浦水系は素晴らしいバスフィールドです。ほぼ全域でオカッパリが楽しめ、ボートからはさまざまなカバーや地形変化が僕たちを出迎えてくれます。そして釣り人による湖岸清掃が実現しているフィールドでもあります。間違いなく日本を代表する素晴らしい釣り場です。
しかし、残念ながら、近年はバスの個体数の減少を多くのアングラーが実感しています。
この先20年、30年とこの霞ヶ浦水系でバス釣りを楽しむためにはどうするべきか……。
これからのトーナメントの仕組みを模索する第一歩として今回はデジタルウエイインを採用することにしました。
これまで、ウエイインショーはオールスタークラシックのボルテージが最高潮に達する場面でした。選手が苦悩と葛藤のすえに釣ってきた1尾をオールスターを愛する大勢の皆様と共有できる、かけがえのない時間です。
ウエイインショーはオールスターのアイデンティティのひとつでした。
しかし、現在の状況と向き合ったとき、審判兼記録員であるプレスアングラーの同船があり、競技の公平性を担保できるオールスタークラシックではデジタルウエイインの道を模索するべきという結論に至りました。
オールスタークラシックに出場する選手は魚のケアに関しても超一流の方ばかりですが、釣った場所と会場が場合によっては遠く、違う水質の場所への移動による魚へのダメージがあることを考慮し、会場での検量は見合わせることとしました。
ウエイイン自体を否定しているわけではありません。あくまでフィールド状況や競技エリアの広さ、全選手にプレスアングラーの同船があるというオールスターならではの特徴を総合的に考えた結果の判断です。
まだ模索段階ではありますが、デジタルウエイインは新しいトーナメントの楽しみ方を作り出すことができる可能性を秘めていると考えています。
帰着後のショーは魚の持ち込みなしで開催します。ビジョン等を使った演出で例年以上に楽しんでいただければと願い準備を進めているところです。どうか、一日を戦い抜いた選手を会場で迎えてください。新しいトーナメントのかたちを目指して開催する34回目のオールスタークラシックを応援していただけると幸いです。
Basser編集長 佐々木徹
■感染症対策について
千葉県による「イベントの開催制限等について」のアナウンスに従い、下記の対策を実施して開催いたします。
会場での感染症対策
・適切なマスク着⽤の周知
・イベント参加者間の適切な距離の確保
・消毒液設置とアナウンスによるこまめな⼿指消毒の励⾏
来場者の皆様へ
・発熱等の症状がある場合はイベントに参加しないでください。
・感染拡大防止のためにイベント主催者から連絡先登録等の求めがある場合には積極的に御協力をお願いします。
・イベントに参加するときは、原則として、マスク(不織布マスクを推奨)を着用してください。また、こまめな消毒や手洗いなど、「新しい生活様式」に基づく行動を徹底してください。
・屋内での休憩時などは「3つの密」の環境を避けてください。
・ご来場の前後は、移動中や移動先での感染防⽌のため、3密の回避やマスク着⽤などの適切な⾏動をとってください。

.jpg)




.jpg)
.jpg)

.jpg)























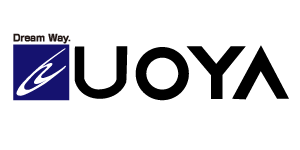














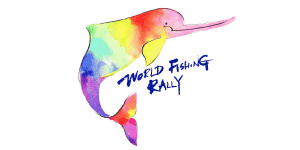










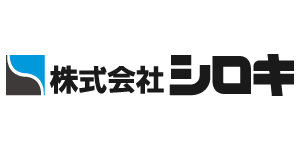





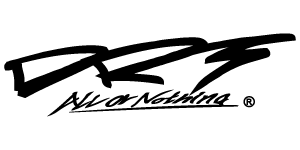


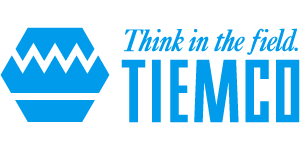




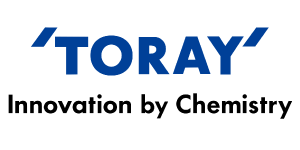




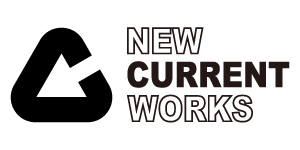












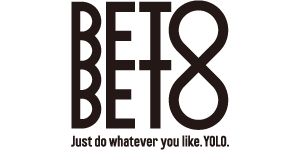


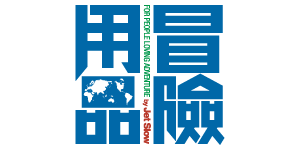






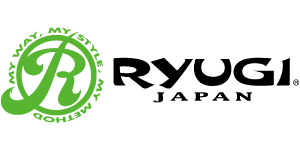









.jpg)

.jpg)







%20(2).jpg)


.jpeg)


.jpg)




.jpg)

